
gegetom
レビュー
8か月の娘を風呂で溺死させてしまった水穂の裁判に、補充裁判員として参加することになった里沙子。裁判を傍聴するうちに水穂と自分を重ね合わせていく。わかる、子育て中の専業主婦の気持ち。社会に置いて行かれた感じ、どこにも所属していない不安。扶養家族という立場ゆえの夫への遠慮。里沙子は裁判を自分劇場として観覧するうち、次第に被害妄想がとまらなくなる。筆者の作品を読むたびに思う。筆者はなぜこんなに私たちのことを知っているのか。直視したくない内心を毎回突きつけられる。
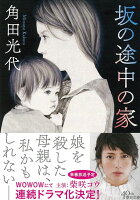
文庫 坂の途中の家
角田光代
本棚登録:87人
こんな展開もありなのか!と驚くも、余白のない筆致にちょっと読みづらさを感じたのが残念。著者の「店長がバカすぎて」や「ひゃくはち」はとても楽しく読めたのだけど、本著や「笑うマトリョーシカ」は著者語りが多いように思った。ストーリーの運び方も結末への辻褄合わせのようなところもあって。でもこの結末で終わらせるとは!雪乃への同情とも憐憫とも何とも言えない感情で読み終えた。
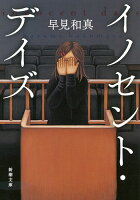
イノセント・デイズ
早見和真
本棚登録:378人
先日読んだ「高校入試」は章の合間にSNSの発言が挟み込まれていたけど、この作品は本編の後に添付されている。最初それに気づかず読んでいた。本編と行ったり来たりするのはちょっと面倒だったかも。ただ、結末を巻末の新聞や週刊誌の記事を読むことで読者が知るのは面白い構成。 もし私が間違って殺人事件をおこしてしまったとしたら、週刊誌は私のことをめちゃくちゃ悪く書くんだろうな、と思ったことがある。この作品は週刊誌やその取材に応じた当事者周辺の人たちを皮肉った作品でもある。湊作品の読み方にも慣れてきた。
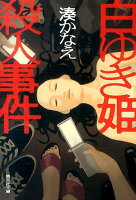
白ゆき姫殺人事件
湊かなえ
本棚登録:0人
「入試をぶっつぶす」という物騒な貼り紙が教室に貼られるところから物語は始まる。舞台は地元一の進学校である一高。登場人物は主に教師。教師の多くは一高出身だ。彼らの愛校心は半端ない。一方、教師の中にはかつて一高不合格となった者もいて複雑な感情を抱いている。読みながら、ああ、そういう問題提起をしているんだぁ、と想像していたのだが、最後に私の読みは逸らされた。学校という閉ざされた社会では、ともすると大人の都合のいいように物事が進んでいく。生徒のために聖域であるべき学校が教師の聖域になっている。
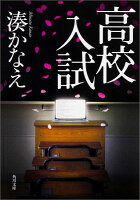
高校入試(1)
湊かなえ
本棚登録:261人
果たして、成瀬が同じクラスにいたとして、私は友達になれるだろうか? 運動も勉強もできる(けん玉や手品も得意)、だが、空気を読まず興味の赴くまま行動する成瀬。 多分、一定の距離をとって観察するだろう。 (関わったら面倒くさい、と) (たが、)そんな成瀬にも島崎という友人がいる。M1出場を誘うほどの仲(?)の友人だ。島崎が成瀬を見る目は厳しくも温かい。 成瀬のぶっきらぼうなセリフからロボット的な口調を想像してしまうが、(彼女にも)感情はあるらしい。最終章で彼女の心の動きがみえてくる。 解説にあるように、成瀬の自由さは周りの人を自由にする。 タイトルの「成瀬」を「自由」に読み替えてみる。きっと誰にとっても過ごしやすい世の中になるのだろうな。 この本を手に取った中高生には、ぜひ、解説まで読んでほしい。 (みんなが成瀬になるために。) 補足 高校入学時の成瀬の自己紹介の場面、サイコー。
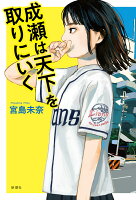
成瀬は天下を取りにいく
宮島未奈
本棚登録:575人
大学生になった成瀬。バイトしたりびわ湖大津観光大使になったり、活動範囲も広がる。そのあたりは他の学生と変わりない。でもやはり成瀬は成瀬。相変わらず「信じた道」を突き進む。今作はそんな成瀬に影響される人々が描かれる。これはまさに前作の解説にあった「成瀬の自由さが周りの人も自由にさせていく」現象。読んでいて小気味よい。また前作同様笑いのポイントも散りばめられている。「コンビーフはうまい」の電話番号とか、西武の跡地に建てられたマンションの名前とか、紅白でのけん玉とか、私の笑いのツボを刺激する。これだから成瀬ファンをやめられない。おっと、成瀬によって自由にされない人が1人いた。成瀬のお父さん。娘を心配する父の気持ちだけは娘からは解放されない。
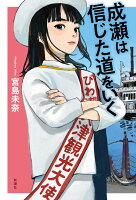
成瀬は信じた道をいく
宮島未奈
本棚登録:410人
序章で早速、知的リテラシーがなければ読み解けない、と釘を刺され怯むも、テレビなどで拝見する著者の、人間に纏わる様々な事象を脳科学で説明するその理論に触れたくて読んでみた。理性が感情に覆われてしまいがちな自分。脳が人をコントロールしているわけだけど、脳の機能を知ることで自分を制御することもできるようだ。自分の脳を臓器の1つとして客観視し、脳を内在する別の人格と思えるくえらいになりたいな。気になった箇所→「大衆が心地よく感じる人は、大衆の思考を止めてしまう。」→この政治家を選ぶ時のポイントは適時でもあり興味をひいた。楽をしたがる脳を制御し、自身で思考し続けねばならないのだ。

脳の闇
中野信子
本棚登録:0人
短編ミステリー5編集。背筋がゾワッとするものや胸がざわつくもの、それぞれ種類の異なる5つのミステリー。私が一番怖いと感じたのは第4話かな。5話目は前4話に絡められた物語になっていて、ドラマを観る時にうっすら感じていた”あるある展開”がコミカルに描かれている。登場人物が実際の役者さんを想起させる名前だったから、より「わかるー!」感が味わえた。著者とこの「わかるー!」感が共有できたのが嬉しかった。
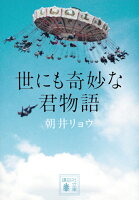
世にも奇妙な君物語
朝井リョウ
本棚登録:191人
並べられて始まった3人の女性の物語。読むにつれ、彼女らの言動から時間の軸が見えてくる。それぞれの物語をその時間軸に当てはめながら読み進めると、徐々に物語が立体的に。とうとう物語から目を離せなくなり、一気に最後まで読んでしまった。読者を物語に没頭させる構成はさすが!薄幸で芯の強い女性の姿に、昭和の昼メロを思いだす。タイトルの「鎖」、繋がりや縁といった見方もできるが、女性を縛る「鎖」とも読めるな。ともあれ、ロマンチックなミステリーだった。
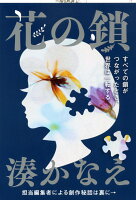
花の鎖
湊かなえ
本棚登録:321人
甲子園が開幕し、高校球児が熱い闘いを繰り広げるなか、一気に読んでしまった。私達は高校球児を「野球に情熱を注ぐ純粋な子」と神聖化してしまうけど、素顔は普通の高校生と変わりない。何が違うかと言えば、甲子園という目標があり、その目標を共有する仲間がいるということ。それがあるから、華の高校生活を犠牲にしてまで野球に打ち込める。でもその仲間の絆にいったん綻びが見えはじめると⋯ めちゃくちゃ青臭い青春小説。この時期に読むと一段と面白い!

ひゃくはち
早見和真
本棚登録:35人
角田光代。なんて嫌な作家なんだろう。私たちの腹のうちをこんなにあけすけに描いて。自分だって見て見ぬふりをしている黒い感情なのに。全てを見透かされてる感じがして読み心地が悪い。でもページを繰る手は止まらない。作中の容子や瞳はまるで鏡に映った自分。彼女らを客観的に観察し受け入れることは、自身を認めること。こうして私はいつも角田氏の作品に責められつつ救われている。
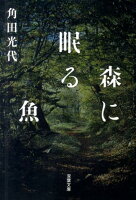
森に眠る魚
角田光代
本棚登録:104人
家庭も仕事もほどほど順調なお父さん7人の物語。「ビタミンF」のFはきっとFamilyのFなんだろう。30〜40代の男性って、主体的に行動できない時期に入ってるんじゃないかな。家庭では奥さんに主導権を握られ、会社では上の意向を窺い仕事をし。でも裏を返せば、流されるまま平穏に日々を過ごしていられるということ。しかし平穏だと思っていた日々に変化が起きる。子供の成長や両親の老いがもたらす変化だ。変化は家族が新たなフェーズに入ったことを示す。それに向き合い、ひとり静かに気合を入れ直すお父さん。エールをおくりたい。

ビタミンF
重松清
本棚登録:159人
短編5編のホラー。始めの2編には花子さんとコックリさんが登場する。名前を聞くだけでも怖いのに、著者はそれをさらに背筋を凍らせるストーリーに仕上げている。気に入ったのは3編目「おとうさん、したいがあるよ」。祖父母の家の掃除をするつつじと両親。その家で死体を発見する。八体も。日常生活の中に死体が八体って。日常と非日常の振り幅が大きすぎ。自分の日常にもリンクしそうでぞわっとする。昔、自分が見てる世界はみんなの見ている世界とは違うんじゃないか、と思ったことがあるけど、もしかして⋯、もしかするかも。

ふちなしのかがみ
辻村深月
本棚登録:96人
推し活というポップな話題を「推し、燃ゆ」と古典的に題し、純文学の語り口で綴られる本物語。全編通して重たい雰囲気で語られる。学校にも家庭にも居場所のないあかりは、推し活することでどうにか生きている。その生き方は蝋燭そのもの。自分を燃やして生きながらえている。なのに突然、推しが引退発表。彼女が推しを失い、「二足歩行できなくなる」ところで物語は終わる。あかりの陥った計り知れない閉塞感。巻末で、人はなぜ推し活にはまるのかを金原ひとみ氏が解説してくれている。

推し、燃ゆ
宇佐見りん
本棚登録:692人
愛すべきキャラ肉子ちゃん。彼女はきっと不幸に陥る思考回路をぷっつり断線してしまってるのだろう。幸せしか感じとらない感受性、というかどんなことも幸せに転じる転感性というか。同じ世の中を生きるなら、こういう思考で生きた方が楽しいよね。でも肉子ちゃんの思考だと、過ちから学ばないから、同じ過ちを繰り返しちゃうんだよな。
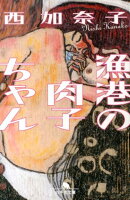
漁港の肉子ちゃん
西加奈子
本棚登録:200人
一目惚れした後輩を金魚のフンのごとく追う俗な学生と、そんな想いには無頓着、酒にめっぽう強い黒髪ぱっつんのフシギちゃん。この二人が京都の街で青春を謳歌(?)する物語。二人をとりまく連中のキャラがまた濃い。年中浴衣姿で天狗を自称する樋口氏、ただ酒大好きおやじ殺しの羽貫女史、偽電気ブランを愛する底抜けな酒飲み、一方では非道な金貸し李白翁、古本市の神様と称する少年などなど。四章で構成されているのだけれど、第三章の学園祭の偏屈王が気にいった。読み終えて、俗学生に「ハッピーエンドで良かったね!」と声をかけたい。

夜は短し歩けよ乙女
森見登美彦
本棚登録:520人
定時制高校の物語だから、訳アリ生徒が先生の力で更生していくんだろうと思って読み始めたが、そんな浅い物語ではなかった。養護教諭が語る「すべてに生徒は救えない。誰が救えて、誰が救えないのか。…トリアージを、結局ここでもやってる。」この本音はきつい。訳アリ生徒達が、藤竹の声かけで科学実験に参加し、順々に芽吹いていく様子をみるのは爽快だ。また藤竹自身も、生徒の科学実験を通して自身の実験をしていたという流れも、教師の一方的な押し付けがなくていい。でもやはり、漏れこぼれ落ちた生徒がいることも気に留めなければならない。

宙わたる教室
伊与原新
本棚登録:181人
金融経済ミステリー。何者かが地方の小さな町の経済を、マネーゲームをするように牛耳っている。その目的は? お金は天下の回りものというけれど、実際は、意図した方向へ回している者がいて、それをまた知識ある誰かが、利己的な別方向へ回していたりして。 お金は水の流れとは違い、低い方から高い方へ流れているような気がする。要はお金持ちに集まるようになっているのだ。それに抗うには金融知識をつけて武装するしかない。少しでも損しないために。もっと池井戸作品を読んで知識をつけよう。

M1(エム・ワン)
池井戸潤
本棚登録:10人
京都に住む狸一家の物語。京都の地名の読み方に慣れず戸惑うも、狸が歩き回る京都の街中を、狸の歩に合わせ観光する気分で読んだ。主人公は天狗に振り回される狸。考えれば天狗が何かをよく知らない。良いものなのか悪いものなのか?結果この物語を読んで、私の天狗のイメージは「煩悩の塊」となってしまった。狸ファンタジーだけど、狸一家の長、総一郎の残した言葉にほろりとさせられる場面が多かった。京都に行きたいな。
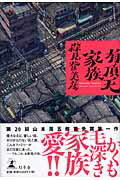
有頂天家族
森見登美彦
本棚登録:0人
出だしは青春成長物語だったが、後半突然ミステリーに。急な転換と、徐々に増える登場人物に混乱しつつ何とか読了。登場人物が多くなるのはミステリーの特徴なのかな。 物語は『清家一郎育成シミュレーションゲーム』といった感じ。登場人物の誰もが、ゲームのコントローラーは自分!と信じているも、突然の強制退場で謎が深まる。 人間が作ったロボットに人類が滅ぼされる、といったSF作品に擬えながら読んだ。 ニセモノなのかホンモノなのか掴みどころのない清家をうまくマトリョーシカで表現している。
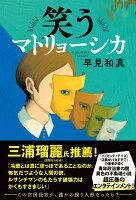
笑うマトリョーシカ
早見 和真
本棚登録:0人