匿名ユーザー
レビュー
イケメンや声の良い男がモテるのはなぜ? 年頃の娘が父親を毛嫌いする理由とは? 実は、動物行動学観点からは当然の成り行きなのだ。 孤立感から招く病気。 血液型は、免疫の型が違うことから区別された、など。 知らなかったけど、「目から鱗」な話が盛り沢山。 世の中を違う視点から見るにはうってつけの内容で、生きていくヒントもいっぱいありました。 病気、特に糖尿病にかからないためには孤独にならないことが何よりも大切。人からコンタクトをとって貰えるようにすることが大切。自分のことを心配してくれる人が沢山いる人ほど糖尿病になりにくいと言うデータがある。 他にも私達人間が地球で生き延びていくための戦略が分かります。 題名の「ウソばっかり!」と言うのはこの本の内容に当てはまらないと思います。 正しくは「それは当たり前」「何となくそうかな?」と、感じていたことの中に人間の生存戦略がある、つまりきちんとした理由がある、ということ。 つまりそれは「ウソではなかった! ちゃんと理由があった!」と言うことではないでしょうか? 竹内久美子先生!

世の中、ウソばっかり!
竹内久美子
本棚登録:0人
喜久雄と俊介。父半四郎からの襲名を受けられず、喜久雄との役者としての格差を埋めることもできないまま出奔した俊介。喜久雄の恋人、春江を伴い放浪の旅に出る。襲名披露で倒れ、帰らぬ人となった半四郎。「親無しは首のないのと同じ」の通り、復帰した俊介と入れ替わるように歌舞伎界で辛酸を舐めた喜久雄。プライベートを暴かれスキャンダルと騒がれる中、芝居の世界に更に没頭していく。 糖尿病で右足切断の後、舞台に立つも絶命した俊介。人生全てを捧げた喜久雄は狂おしいばかりの歌舞伎役者。 凄まじい人生を生き抜く喜久雄にとって、ただ舞台での恍惚感だけが生きがいとなっている。 舞台の上から歴代の役者から見られているような神々しい瞬間が堪らなく愛おしく感じられる…。 人間国宝となるような人は、皆、同じような神々しさを感じながら生きているのかもしれない。 .
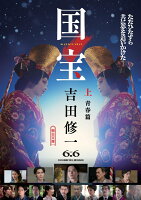
国宝 上 青春篇
吉田修一
本棚登録:220人
風早の街に50年の歴史を持つ星野百貨店。そのステンドグラスに描かれている白い猫が、本物の猫になり、それを見た人の願いを叶えてくれると言う。 コンシェルジュとして赴任してきた芹沢結子が絡む不思議で心暖まるストーリーが次々と展開されていく…。

百貨の魔法
村山 早紀
本棚登録:0人
人間は、自分の顔、そして自分の姿を自分で見ることはできない。鏡や他人を通してしかその全体は掴めない。自分から見える一部から想像するしかないのだ。そう考えると不思議でならない。 ファッションは、自分をどのような社会に登場させるか、その社会的ディスプレイのスタイルだとも言える。 最近までファッションを語ることが 軽視され、冷笑されてきた。 しかし、コスメ、エステ、ボディメイク、美容整形をも含め、自然な自分の体型を苦痛を伴ってでも「理想のカタチ」にしたいという現代社会にあって ファッションもその重要なひとつだと思う。そう考えるとなかなか奥深い。 これからの「お洒落の基本」は、何になるのか? それは「ホスピタリティ」だと作者は語る。相手を歓待する気持ち。 団扇で風を送る、暑いのに呂や紗 の着物を重ね着する、話をするより聴いてあげる… お洒落とは、自己主張するだけでなく、他人の視線をどのようにデコレートするのか。そんな小さな思いやりがお洒落の基本になればどんなに素敵だろう。まさにパスカルの「繊細のエスプリ」となる。 ファッションに関わるしごとをしきた私にとっての意義を考えさせられる一冊となった。

ひとはなぜ服を着るのか
鷲田清一
本棚登録:0人
この本を読み終わった後、友達が一人増えた。小澤征爾さんだ。 彼の好きな食べ物は何か、何に感動し、どう生きたいと思っているか、どんな友達がいるか、家族をどれだけ大切に思っているか。 小澤さんの好きな食べ物を持って行っら良いか、どんな話をしたら喜ぶか、私の友達の内、誰を紹介したら話が盛り上がるか… そんなことが分かる本でした。 1960年代の世界を肌で感じた小澤さんだからこそ伝わってくる物がありました。彼の素直で、みずみずしくて、少しやんちゃな目線で見た欧米の姿が良く分かります。 彼の晩年は音楽があればこその闘病生 活だったのだと思います。 元気の出る本でした。

ボクの音楽武者修行
小澤 征爾
本棚登録:0人
「皇室」と言う特別な環境にお生まれになった浩宮様。そして特別な環境に嫁がれた上皇后美智子様。そして、戦後の皇室の有方を問われる立場の上皇様。将来天皇になられる浩宮様をお育てになられるに当たり、並々ならぬお気持ちで愛情を注がれ、浩宮様の皇室のそして日本の未来をも見据えた考えで1日1日を大切に接して来られた上皇様と上皇后様。 そのお考えを良く理解し、お忙しい両陛下よりもたくさんの時間を浩宮様と過ごされた浜尾さん。 両陛下のお考えが同じであり、先の先まで考えた子育てに感服する場面も多々あったようだ。 やはり、良い子育ては夫婦が仲良くすることが一番の秘訣。 そして、「子育ては先の先まで考え抜いて行っていく」と言うことの大切さ。それを実行されているのが上皇様と上皇后様だと痛感した。 日本国民の日本家庭のお手本であり、理想だと思う。 浜尾さんの「情操教育というのは、日常行動を通して目に見えない微粒子が移っていくような形でなされるものである」と言う下り。 浜尾さんが盲腸で浩宮様の卒園式を欠席した折、両陛下が病院にお見舞いに来られたお姿を見て強くおもったそうだ。人を育てることの尊さを感じる一冊。

浩宮さま
浜尾 実
本棚登録:0人
大島屋の隠居小兵衛からの注文がどうやって新宮屋に来たのか、川並の建次との出会い。新宮行きの船中で知り合った水戸藩士三人。最後の買い付け交渉の場で祥吉は自分の素性を明かすが その人柄を信用され、建次からも水戸藩士からも咎められることなく無事に買い付けを済ませる。 江戸時代の船旅の困難さや江戸と新宮の違いや当時の賑わいがとても良く分かる。そして何より、どんな稼業をしていても堂々と自分の考えに従って生きていくことの大切さ。人間として大切にすること、潔い態度が人を動かす、と言うことが良く分かった。 ただ、小説として残念なことがある。前半の面白さに比べて、結末が少しみすぼらしく感じられる。道中、大次郎の素性がバレてくるところなどスリルもあり、建次が新宮に慣れていく場面や水戸藩士のエピソードなどとても納得がいき、一つ一つ感動できる。 しかし、水戸藩士三人がいかに命を掛けているかが理解できると言う説明の為に、祥吉が自分の素性を目の前で明かすのか? しかもどのように明かしたかは、詳しくは書かれていない。 祥吉がどれだけこの大仕事に思い入れがあるか、と言うことに繋がるのだろうが、動機付けにしては、私にはとても弱い感じがする。 少し、結末が残念な気がする。 (一力さんの作品には、こう言う傾向か少なからずある。忙しくて結末を急いだのかな?とも思ったりする)

いかだ満月
山本一力
本棚登録:0人
自分自身のことをここまで冷静かつ客観的に描いた人は、作家でもなかなかいないような気がする。 義母から「不幸な娘。お金の取れる女優」としか扱われない関係もバッサリ割り切っている。 そして、谷崎潤一郎、川口松太郎や梅原龍三郎などの作家や画家、東海林太郎に可愛がられたこと。杉村春子や田中絹代、成瀬巳喜男、木下恵介との交流など、貴重なエピソードも見逃せない。 これを読めば、戦前・中・後の映画界 のこともほぼ分かると言う年代物でもある。 秀子さんの頭の良さ、決断と思い切りの良さ、そして優しさを口だけではなく行動で表せる人間性が、周囲の人から可愛がられる要因だと思う。 独身時代、家庭には恵まれなかったが 子役の頃からの人間性を見抜く力で 周囲を惹き付け、幸せを手にしたのではないか。 それは、自分の運命を恨むのではなく、ただ受け入れ、カラッと笑ってその時にできることを精一杯やってきたからだ、と言う気がしてならない。 「明るい人」とは、こんな人のことだろう。明るくできるのは、そんじょそこらの生半可な根性では到底できないことだ。 尤も本人は「私には、そんな気持ちも時間もあるかい!ただ只管仕事に追われていただけよ❗」だとアッサリ言うだろう。なかなか読み応えのある作品だった。こんな自叙伝が書ければ最高だと思う。

わたしの渡世日記 上
高峰 秀子
本棚登録:0人
1930年(昭和5年)放浪記がベストセラーとなり、その年、中国満州・上海旅行に行ったのを皮切りに、1931年シベリア鉄道でヨーロッパ、パリに滞在。1932年ロンドンに滞在。 その後も日本国内を旅し、まさに放浪した作家だった。 戦前の海外事情や樺太、シベリア鉄道など、今では経験できない情景が描かれていて、とても興味深かった。 それにしても当時の女一人旅がどんなに勇気のいることか、林先生の好奇心と勇気に感服するばかり。 言葉でなはく、相手に興味を持つ、相手を受け入れることが時代や人種に関係なく如何に大切なことか、良く分かる気がする。地球上の人間を理解したい、と言う林芙美子の情熱が感じられた。

下駄で歩いた巴里
林芙美子/立松和平
本棚登録:0人
国際線のパイロットは、仕事の半分を夜フライトしている。 空の青と海の青。様々な気象、宇宙条件であらゆる種類の「青」を見ることが多い。一番好きな色は「ブルー」というクルーが多いそうだ。 そんな世界があることを知るキッカケとなったことは大きい。 夜の白ナイルと青ナイル、月明かりに照らされる水面、城壁で囲まれた都市、山手線が走る円の都市東京。 ケープタウンプ、イスタンブール、コペンハーゲン、確かな位置を把握していなかった都市。ウプサラ(スウェーデン)など地名も知らなかった都市。 一つ一つ地図で確かめながら、描かれた風景を想像する楽しさに惹かれた。 中学時代、夜中に城達也さんのラジオ番組「ジェットストリーム」を聴きながら海外に憧れていた頃を彷彿とさせるエッセイだった。 新たな視点で世界を見る機会を得た。

グッド・フライト、グッド・シティ
マーク・ヴァンホーナッカー/関根 光宏/三浦 生紗子
本棚登録:0人
「どんな人生にも意味がある」 フランクルの考えを分かりやすく 諸冨先生の体験を通して等身大で解説。
![[新版]どんな時も人生に「Y E S 」と言う](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6872/9784569856872_1_2.jpg?_ex=200x200)
[新版]どんな時も人生に「Y E S 」と言う
諸富 祥彦
本棚登録:0人
7人に共通するのは、目先の利益だけではない、遥かに大きな目標を持って生きていたこと。それを貫く為に、自分だけではない、日本や世界を見据えていたこと。そして、今だけではない将来を見通して行動を起こしたこと。 何が大切で、将来に繋がるかを見極める力があったことが大きい。彼らがいればこそ、今の日本がある、と言える。

戦前の大金持ち
出口 治明
本棚登録:0人
マーニーは、アンナの祖母であるマリアンだった。マリアンの娘エズミは最初の結婚でマリアンナを授かったが、直ぐに離婚。再婚相手とのハネムーンの途中、交通事故で亡くなってしまった。娘のエズミの子マリアンナを幼い頃から育てていたマリアンは、娘夫婦が亡くなったショックから立ち直れず、その年重い病気で命を落としてしまった。幼い頃寂しい思いをしたことから、娘エズミの子、マリアンナを殊の外可愛がっていた。児童ホームに預けられたマリアンナは、プレストン夫妻に引き取られたたのだった。 この不思議な話は、人間の本質について語っているような気がしてならない。人の遺伝や柵、思いが絡み合い、 その時に繋がった人々と織り成す布のようだ。それには愛情が大切だ。

思い出のマーニー
ジョーン・G・ロビンソン/高見浩
本棚登録:0人
西洋絵画の見方を詳しく説明してくれている。基本的な知識から時代背景、画家の人生など、次回から美術館へ行くのが楽しみになる。 「絵画は精神的なもの」と言うレオナルド・ダ・ヴィンチの言葉が心に響く。同じ絵を観ても、今までとは違うものが見えるような気がする。
ネタバレを読む

カラー版 名画を見る眼1
高階 秀爾
本棚登録:0人
国を越え、言葉を越えて人と出会い、絆を深めていくことの難しさ、苦労。 そしてその困難があればこそ、知己の友となれる喜び。 私にもそんな経験ができればとも思い、現在関わっている人の中にきっとそうなれる努力が必要だと感じさせられた。まず、自分が何をしたいのか、何が好きかをハッキリさせて貫くことが一番だと思った。そして今の繋りを 大切にすること。 オックスフォードで学位を取ることがどんなに辛いことか、分かった気がした。チュートリアルで教授と1対1のレクチャーがあり、逃げやごまかしは利かない。最後まで「何を伝えたいのか」核心部分まで突っ込まれる。 しかしそれは、人間の生き方を問われることと同じだと思った。 私もいつか、素敵な経験をしたいと思った。
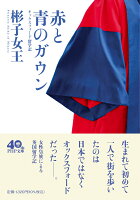
赤と青のガウン
彬子女王
本棚登録:149人
フレッドは、妻が亡くなった後もデトロイト美術館所蔵のセザンヌの妻「オルタンス」にしょっちゅう会いに行っている。美術館の所蔵品が、デトロイト市の財政破綻によって売却されるかもしれない、となった時に500ドルの小切手を握りしめ、チーフキュレーター、ジェフリーに会いに行った。 一人の市民がチーフキュレーターを動かし、裁判官の心をも動かした。 寄付を集めることで、コレクションも年金受給者も救ったと言う話。 デトロイト市民フレッド、コレクションの基となる作品を集めたタナヒル、チーフキュレータージェフリーの三人の観点から書いている点が興味深い。 裁判官クーパーの「グランドバーゲン」と言う考えが形となり、目標額を達成できた。 フレッドのような市民がいることを誇りに思う、あなたがいてくれたからこそ奇跡は起こったというジェフリーが、彼に伝えた言葉にこの話の総てが集約されていると思う。
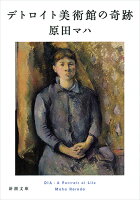
デトロイト美術館の奇跡
原田マハ
本棚登録:86人
独特のストーリー展開に、なぜか引き込まれてしまうものがある。 舞台女優で売れない画家と結婚した祖母。画家は有名になったが若くで他界。娘は額縁職人と一緒になり画家の道を進むが、夫婦とも飛行機事故であっけなく亡くなる。 残された孫達に、厳しくも本質を突いた言葉で彼女なりに励ます。 サーカスの空中ブランコに夢中になった弟。人生は、あちらの世界とこちらの世界を行ったり来たりするブランコのよう。喋れなくなった自分とクラスメイト、亡くなった両親と私達姉弟。 行方不明になった私と弟。それもまたブランコのよう。 そしていつか必ず弟は、戻ってくる、 向こうに行ったブランコが、必ずこちらに帰ってくるように。 この話の中では、祖母の人生を達観した厳しい言葉が姉弟を成長させる。 祖母が意外と重要な役割を果たしていると思う。私もまた人生の中、一日の中で、小さなことを決断し、あちらとこちらのブランコを押しているようなものだと思う。 人生で人に出会うことも空中ブランコのよう。一瞬、手を繋げるだけで幸せと言える。そして押したブランコは、必ずこちらに戻ってくる。 著者いしいしんじの大ウソつきの世界に少しハマってしまった。

ぶらんこ乗り
いしい しんじ
本棚登録:0人
中・高・大学と、周囲を気にせず、自分の大志「地域に貢献する」に向かって突き進んできた成瀬。京大に現役合格するほどの頭の良さを持っていても それをひけらかすこともなく、人に媚びることもせず、淡々と自分の信じる道を進んで行く。間違えたことは素直に謝り、知らないことは教えて貰う。 他人とは違う、変わった所がある成瀬のこの「堂々とした」そして「淡々と進んで行く」姿に人は惹き付けられるのではないでしょうか? 経済格差、パワハラ・セクハラと闘い ながら効率化を厳しく追及される現在。自分の信念をしっかり貫き、奢り高ぶることなく、ブレないで淡々と生きていく成瀬。 その姿が現代人の憧れとなっているのでしょう。私も「成瀬」を忘れず生きていきたいと思います。
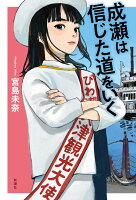
成瀬は信じた道をいく
宮島未奈
本棚登録:410人
ヘレンケラーの話を日本に置き換えた小説。確かに三重苦の主人公「れん」と去場安との激しい葛藤にはとても厳しいものがある。物には名前があり、意味がある、と言うことを理解するまでの苦悩が詳しく書いてあり、それは臨場感のある展開だった。 しかし、れんの少女時代に出会った唯一の友達「キワ」とわずか3ヶ月足らず別れざるをえなくなってからの展開は書き急いでいる感じがした。 キワが津軽三味線の人間国宝に認定され、何十年振りかにれんと再開した時の描写には感激できるものはあまりなかった。 二人が別れてからの繋がりがとても弱い感じがする。 少し残念だった。 しかし、日本には盲目の方の生きる道があり、受け入れる社会であったことに今更ながら気付いた。 差別はあったものの、昔から多様性のある人を生かす道を持っていた国であったことにこの国の懐の深さを感じた。
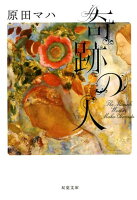
奇跡の人 The Miracle Worker
原田マハ
本棚登録:147人
マティス、ドガ、セザンヌ、モネ の4人の印象派画家に関する話。 全て本人が主人公ではなく、各々の画家の近くにいる人から見た画家の姿を描いている。 助手、ライバル、美術商の娘、義理の娘から見た画家の姿。 セザンヌに関しては、美術商タンギー爺さん(ゴッホも描いている)の娘がセザンヌに宛てた手紙、と言う書き方をしている。つまりスポットライトをどこから充てているかで、画家の姿が違ってくる…みたいな、不思議な感覚。 マハさんの上手いところは、史実を充分踏まえた上で史実と史実の間の隙間を際どく突いてストーリーを展開するところだ。 「そうだったんだ❗」と、決して納得してはいけないのに、つい納得させられてしまう。 でもそれが、画家の本当の姿かもしれない、と思わせるところが上手いと思う。なまじっか知識がある人ほど引き込まれて、騙されてしまうと言う感じがする。知識が中途半端だからこそ引き込まれてしまうのかもしれない。 但し、画家の人柄はとても良く表現されていると思う。人柄を感じることが出来れば、また絵も深みが増す。 マハさんを読む前と、読んだ後では雲泥の差がある。 また展覧会に行ってみよう。
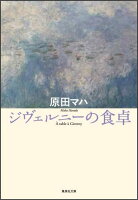
ジヴェルニーの食卓
原田マハ
本棚登録:162人