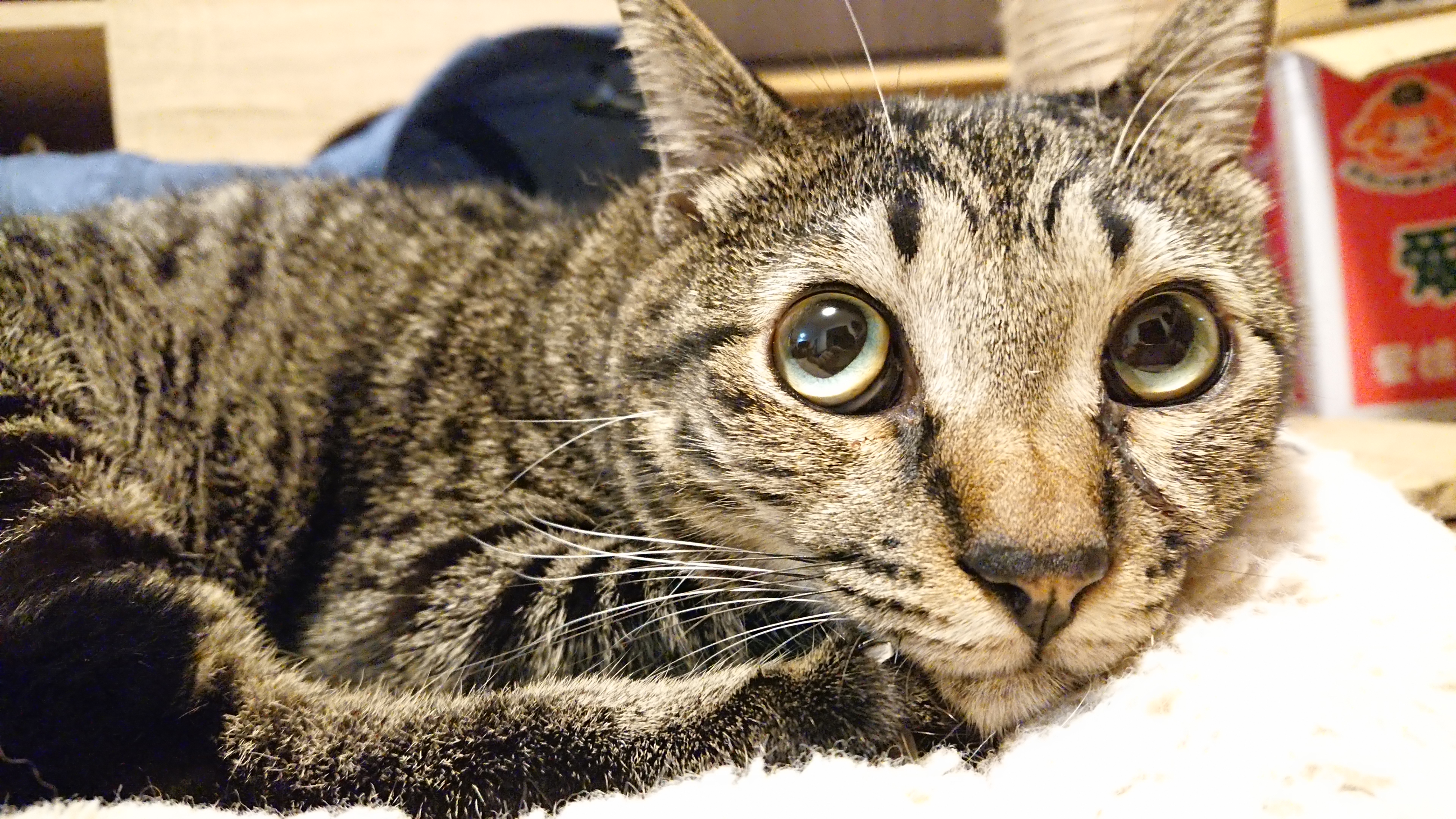
シャケ
レビュー
今ここに在る生は、過去の生の歴史と共に在る。 壮大な生命なる舞台の幕は、私たちが生まれる前から上がっている。私たち人は、その中途から舞台に参加したに過ぎない。 しかし、どんな形であれ、どの生物も役者であることには変わりはない。 この舞台は未だなお現在進行形であり、一つ一つの生が形作る舞台の存在は、この私たちの生が在る事実によって疑い得ない。 私たち、生物を利用する人が在る事実は、彼ら、過去の生命が在った事実でもある。私たちの人生は彼らの歴史の上にあるのではない。今この時、生命の歴史の粋がこの地球にあらゆる生物の形で在る事実によって、私たちの人生は彼らの歴史と共にある。 私たちは個人の人生と共に、その歴史の舞台をも創って行かざるを得ない。悲哀に暮れようが、歓喜に踊り狂おうが、平静に過ごそうが、生きるとは、一つの歴史を創らざるを得ない。そういう認識と壮大な生命の歴史に思いを馳せる時、あらゆる生物に対して寛容にもなれるだろう。 そして、その立場からのみ、自らの人生を立派に生きようとする信念も生まれる。 生命を観る作家の眼は、遠い果ての生命の歴史から近い親しい人々の人生まで同じ眼差しで見つめていた筈だ。 この絵本からは、そういう信念しか感じる事は出来なかった。しかし、それで充分だとも感じた。 あらゆる生物に対して恭敬を自覚して人生を送る決意と、環境保護などという大それた偏愛で自然を見つめてはいないだろうか。という問いを読了後は感じてしまう程、遠い歴史の壮大さから、今ここの一人の人生の極小さにまで収斂し、自らの生を見つめざる得ない鏡面的な作品である。 人が社会の中で生きるとは、他人や外側との摩擦の中で揉まれる事だが、他人やら環境やら何か外側の責任にするのにも切りがない。自身を変えていった方が容易い様に思われる。しかし、それは苦労を伴うものだと理解しているから、人々は中々変わろうとはしない。 だが、生物の進化とは、その苦労を伴った自身の変化に他ならないのではないだろうか。どうにもならない外側に対してのあの多種多様な変化には、生きる決断の強さをまざまざと見せつけられる。 外側を利用する生物はいても、外側に対して決して嘆き立ち竦む生物はかつていなかった筈だ。

せいめいのれきし
バージニア・リー・バートン/いしいももこ
本棚登録:0人
人が生きているのに意味はないが、人生には意味が付せる。そんな人の空しさが根底には流れているのだと思えてならない。

養老孟司特別授業『坊っちゃん』
養老孟司
本棚登録:0人
読めない心を無理に読もうとすると、彼の個性は何処かに散逸してしまう。しかし、同じ心が自身にもあることが、彼の詩を感じるということに幸いする。

山羊の歌
中原中也/佐々木幹郎
本棚登録:0人
苦しみという“存在”は変化することなく、永遠不滅に人の中に存在するのではないか。 苦しみを止滅した人であろうと、外傷を受ければ、やはり苦しいのではないだろうか。 僕らは“存在”が在ることしか知り得ない。その“存在”がどのように存在するようになったのか、は問えない。その事を仏陀はよくご存知だろう。

ダライ・ラマの「中論」講義第18・24・26章
ダライ・ラマ(14世)/マリア・リンチェン
本棚登録:0人
芸術や哲学、文学にも議論が及んでいるため、邦題はナンセンス。 原題訳のままの方が良かったのでは。『現実は目に映る姿とは異なる』

すごい物理学講義
カルロ・ロヴェッリ/竹内 薫
本棚登録:0人
情念の動きを冷静に分析しながら、これによって、訓練される知恵を告白しているところが、一番魅力がある。 また、なぜこれらの情念の言葉の意味を僕らは互いに了解できるのか。 僕の喜び、悲しみでもなく、また、君の喜び、悲しみでもない。喜び一般、悲しみ一般の言葉をなぜ、僕らは了解できるのか。 これら一般に了解される言葉には、いつでも、プラトンの影が見え隠れする。

情念論
ルネ・デカルト/谷川多佳子
本棚登録:0人
人にとって、想像と記憶は社会で生きていく上には欠かせない資質であり、現実に幅を利かせている。 しかし、今を犠牲にした未来などに、僕らは充足し得ないだろう。 なぜなら、僕らは今にしか生きてはいない。 もし、何十年後の未来になっておじいさんになったとしても、おじいさんになった僕にとって、その未来は「今」なのだから。

生き物の死にざま はかない命の物語
稲垣 栄洋
本棚登録:0人
流れる様な文体を追うと、自身からの持ち出しが多く、本を読んでいた眼が、いつのまにか自分自身に向いていたことに気づく。その眼によって、やっと、より自分自身を知ることができる。 読了後は沈黙と感嘆のみ。 惚れる。

考えるヒント
小林 秀雄
本棚登録:0人
今までチーズが苦手でした。 ワインと共にチーズを味わい始め、こんなに美味しい組み合わせがあることに驚きました。 今ではチーズのみでも美味しく味わえるようになりました。 思うに、人との関係もこのようだと思います。 人は、それぞれ先入観や偏見で他人を見ていると言われています。 自身の例で言えば、チーズへの嫌な先入観を勝手に持っていたが、ワインという違う見方を持つことで、嫌な先入観を外すことができ、良い付き合いができるようになりました。 違う見方を手に入れることが重要なのだと思います。 それには興味という自身の一歩がきっかけになると信じています。

図解 ワイン一年生 2時間目 チーズの授業
小久保 尊/山田 コロ
本棚登録:0人
列に並んで前ならえができない。 それは、何かに違和感を感じてその正体を掴もうと、今は列から離れているだけなのかもしれないし、何かに夢中になって必死に追いかけている最中なのかもしれない。 いずれにしても、それぞれに固有の問いを納得しなくては、列に戻って前ならえができない人たちがいる。 現実の世の中の基準からみれば、一巡りして、はじめて普通の人と同じ水準に達することができるだけのことなのだが。 でも、実は誰でもそんな一面があったし、いつもは忘れているだけで、あるのだと思えてならない。 何食わぬ顔で列に戻って前ならえしている人もたくさんいる。 素直に前ならえできた人はそれはそれでいいのだ。 だけれど、素直に前ならえできない人もいる。 そんな〈子ども〉のための本書です。 しかし、世の中の人の自己意識が、〈子ども〉という自己意識よりはっきりしたものだと誰に言えるのだろうか。 〈子ども〉の様に、烈しい問いの襲来と戦わねばならなかった人は、それゆえにいよいよ研ぎすまされた鋭い意識を持つ様になるのだろうか、 それとも世の中の人は、正気のお蔭で、鈍い自己意識に安住しているのではないのだろうか。

〈子ども〉のための哲学
永井 均
本棚登録:0人
動物は言葉を話さない。その事によってペットは無条件で愛せるのかもしれない。 人に対してもそうしたいものだけれども、言葉というものは一つの障害になり得てしまうのだろう。

ねこバカ いぬバカ
養老 孟司/近藤 誠
本棚登録:0人