あきりん
レビュー
主人公の郁子のまっすぐな姿勢と実行力はとても魅力的で、読んでいて心が晴れやかになるほどです。何十年も誰も手をつけられなかった改革に、「どうすればできるか」と集中し、周囲を巻き込んでいくそのエネルギー。都会から来た人だからこその鋭い視点も、地域を変える大きな力になっていました。 私たちは、まるで“ゆでガエル”のように、環境に慣れてしまえば変化をあきらめ、他人を責めることだけは上手になっていきがちです。でも、古い慣習に染まらず、理想を抱き続けるには仲間が必要。そして、名もなき人々の「変えたい」「変わりたい」という想いこそが、世の中を動かしてきた原動力だったはずです。 過去の歴史から学び、未来をあきらめず、「今」の自分に何ができるかを考え、行動する。そんな生き方こそが本当にカッコいいのだと、郁子の姿から教えられました。自分自身もそう在りたいと、心を奮い立たせられた一冊でした。

あきらめません!
垣谷美雨
本棚登録:13人
「子どもめし」なんて言葉もなかった私の子ども時代。母子家庭で、昼も夜も働いていた母。土曜日のお昼は、いつも友人の家でごはんをごちそうになっていました。 あの頃の私は、卑屈になることもなく、 ただ「おいしいな」「ありがたいな」と感じていられた。 それは、友人の家族のあたたかな思いやりのおかげです。 そしてその感謝の気持ちは、大人になった今、より深くしみわたっています。 子どもにとって、「貧乏」はどうしようもない現実。でも、満たされた胃袋は、確かに血となり肉となり、そして心を育ててくれました。 あの頃、近隣の人たちは、貧しかった私たち家族にとても優しかった。 「ここは安心していい場所だよ」と、黙って示してくれていた。だから私は、世の中に拗ねたり、恨んだりせずにいられたのだと思います。 そして今、恥じることのない大人として、その恩に報いたい。いただいた優しさを、今度は私が次の誰かへ。ペイ・フォワードで、温かい記憶を届けていきたいと思います。
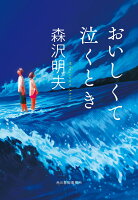
おいしくて泣くとき
森沢 明夫
本棚登録:0人
サイキックという特殊な能力を持っていることと、その能力をどう使うかは、まったく別の次元のこと。 吉本ばななさんの独特な世界観に触れて、「この人には、見えている世界が違うのだ」と、謎が解けたような気持ちになりました。 自分を育んでくれた【下町】という土地の、大らかさやいい加減さ、懐の深さ、単純さ、そして優しさ。 そうした背景があったからこそ、特別で少し一般的ではない能力を、「異質なもの」として扱うことなく、ごく自然に受け入れ、溶け込むことができたのだと感じます。 そんな環境への感謝と愛情が、物語全体にやさしく綴られていて、「今、この気持ちを記しておかなければ」と思わせられました。 しみじみと、人間への賛歌だなあと、あたたかい気持ちに包まれました。 私たちは、育った環境や出会った大人たち、学校の風土、親の生き方などから大きな影響を受けています。 そのすべてを“運命”として受けとめながら、「私はこの世で何をするために生まれてきたのか?」という問いを、人生という冒険を楽しむように味わっていきたい。そんな思いを抱きました。

下町サイキック
吉本ばなな
本棚登録:39人
この本は、「思いを言葉にして伝えられること」が、どれほど尊くて幸せなことかを、あらためて気づかせてくれました。 一つ目の奇跡は、「言葉が使えること」。 そして二つ目の奇跡は、「その言葉で、思いを届けたい相手に、ちゃんと届けられること」。 それがどれだけの恵みや奇跡の積み重ねのうえにあるのかを思うと、日々のやりとりさえも愛おしく感じます。 人は、生まれてから少しずつ言葉を覚えていきます。けれど、どんな言葉を覚えるかは、育った環境によって違ってきます。 特に「感情を表す言葉」は、身のまわりの大人たちが日々どんなふうに言葉を使っているかが、とても大きく影響するのだと思います。 やさしさや感謝に満ちた言葉がそばにあれば、そのような気持ちが育ちやすくなり、反対に、乱暴な言葉ばかりが飛び交う環境では、心の表現も偏りやすくなるのかもしれません。 私たちは、言葉を使って考え、感じています。 「はじめに言葉ありき」という言葉のとおり、言葉は人生の土台にもなっているのですね。 本の中では、安先生という教育者が、知識や教養だけでなく、言葉の力を通して一人の人生に奇跡を起こした姿が描かれていました。 子どもたちと関わる大人が、どれほど大きな影響を与える存在なのか──私たち一人ひとりが、そのことにもっと自覚的でありたいと思いました。 家庭では親の言葉が、職場では上司や同僚の言葉が、そして社会全体の空気が、私たちの日常や心のありように静かに、けれど確かに影響を与えています。 だからこそ、「どんな言葉を使うか」は、とても大切な選択だと思います。 言葉は時代とともに変わっていくものではありますが、それでも、「言葉が人をつくる」ということを忘れずにいたい。 その素晴らしさと同時に、時に人を傷つける怖さも、しっかり心にとめておきたいと思います。 私たちは、言葉によって人間らしくなっていく。 そんなふうに、もっと言葉を大切にしながら、自分の思いや感情を丁寧に育てていけたら…と、やさしい気持ちになれる一冊でした。
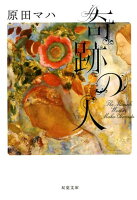
奇跡の人 The Miracle Worker
原田マハ
本棚登録:147人
世の中で起きる様々な事故や事件に対して、当事者ではなく、間接的に影響も受けていない立場であればこそ、冷静に、客観的に考えることができるのだと思います。そんなとき、私たちは思いやりにあふれ、優しく寛容な人でいられるのかもしれません。 けれど、それが自分の身にふりかかり、我慢を強いられるような立場になったときにも、同じようにいられるのでしょうか。受け入れ、優しくあることができるのでしょうか。 実際に自分が当事者になったとき、自分の中にある矮小さや意地悪さ、ケチな傲慢さや横柄さに驚かされます。他人事のときには見えなかった、無責任な自分の姿にも気づきました。私は「善人の顔」をして、普段は「菩薩の修業中」などと語っているくせに、これで本当に修業中と言えるのか?と、自分に問いかけずにはいられませんでした。 そんな自分に向き合う一方で、「誰かを守ってあげたい」という衝動に突き動かされる、自分の中の“善”の存在も確かに感じています。 だからこそ、必要以上に自分を卑下することなく、愚かでかっこ悪い自分も認めながら、菩薩を志すという道を通して善なる自己を育てていきたい。そしていつか、社会の中で誰かの役に立てるような自分でありたいと願っています。
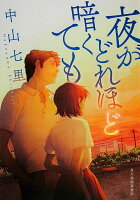
夜がどれほど暗くても
中山七里
本棚登録:0人
生物学的に「本当の親」とは誰なのか。育ててくれた人こそが本当の親なのか。 どちらが正解かなんて、世間の物差しで測る必要はないと思います。 大切なのは、「自分にとって親だと思える、かけがえのない存在かどうか」。 その人のことを思うと、慈しみの気持ちがあふれてきて、命がけで守りたいと思える。 喜ばせたい、悲しませたくない、甘えたい、慰められたい、笑い合いたい——。 そんな願いが自然と生まれてくる人こそ、本当の親だと思えるのです。 人生の彩りなど知らなかった、まっさらなキャンバスに、どんな色を重ねてもいいよと、 いいも悪いも受け止めてくれる、揺るぎない土台のような存在。 そんな絶対的な愛を教えてくれたその人こそが、私にとって「本当の親」だと心から思えるのです。

籠の中のふたり
薬丸岳
本棚登録:63人
「魂が震えるほどの愛を知ったとき、人生が動き出す」 人は、誰かに必要とされ、愛されたときにはじめて「自分がこの世に存在している意味」を実感できるのだと思います。 ただし、一方的に注がれる愛情は、与えられることが当たり前になってしまうと、その価値に気づきにくくなるものです。 けれど、自分の内側から誰かの愛を強く求めたとき──そのとき初めて、愛が満たされない苦しさや不安、心の拠り所のなさに気づかされます。 もちろん、人との関わりはマイナス感情だけをもたらすわけではありません。一瞬の輝き、ときめき、安心感、満たされる喜び…。そして何より、「自分という存在には意味がある」と思えることが、生きる力につながるのです。 人は生まれてから死ぬまで、ずっとそうした出会いを求めているのではないでしょうか。 それに気づかないまま、ただ日々を過ごしていることもあるかもしれません。 人生には、受験、友人関係、就職など、さまざまな出来事があります。成功や失敗を繰り返しながら、他人との関係はもちろん、自分自身との向き合い方も変化していきます。そうして達成感や幸福を追い求める中で、本当の意味での「幸せ」とは何かが、少しずつ見えてくるのかもしれません。 けれど、「自分の幸せ」に執着しているうちは、心からの歓びには出会えないのだと思います。 やはり人は、人との関わりの中でこそ、深く満たされる体験や、生きる喜びを感じられるのではないでしょうか。 たとえ他人から見て不幸に思える状況であっても、大切な誰かに必要とされ、魂が震えるほどの歓びを感じた瞬間があったなら、その人の人生はきっと「幸せだった」と言える──私はそう思います。
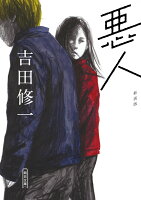
悪人 新装版
吉田修一
本棚登録:23人
人が人を“丸ごと”信じることの難しさ、そしてそれでも「信じたい」と願う気持ち。この感情の根底には、「自分も誰かに信じてもらいたい」という願いがあるのだと感じました。 「信じられたい」とは、自分の存在をそのまま受け入れてもらえるという安心感であり、そこにいてもいいと思える心の居場所です。つまり、承認されることによって、私たちは自分の価値を感じられるのだと思います。 一方で、「信じられていないかもしれない」と感じるときの、あの居心地の悪さ。信頼されるというのは、簡単なようでとても難しいことです。 だからこそ、まずは自分から。相手を信じる姿勢が、信頼の輪を広げていく一歩になるのだと思いました。
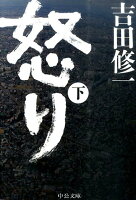
怒り(下)
吉田修一
本棚登録:134人
家族にしか分からない、悲しみや寂しさ、執着、憧れ、独占欲、飢餓感、そして幸福感。 親としての責任感や愛情のつもりが、逆に相手を息苦しくさせ、追い詰めてしまうこともある。 そのせいで、心の距離をどう取ればいいのか分からなくなるもどかしさが生まれる。 他人なら見えることが、家族だからこそ見えない。 特に親子は、始まりから強く結びついているぶん、相手のすべてを理解しているような錯覚をしてしまう。 でも、どれだけ近くにいても、子どもには子どもの人生があり、思いは完全には重ならない。 「命と引き換えてもいい」とさえ思っているのに、どうしてこんなにすれ違ってしまうのだろう。 夫婦は、もともと他人だからこそ、違いを前提にして関係を築ける。 そのぶん、割り切れたり、距離を調整する余白がある。 ある意味で“偽薬”のように、救いになることもあるのかもしれない。 だから、努力しようと思う。 どんな関係性も、「ありのまま」だけでは理想通りにはいかない。 家族も、親子も、夫婦も――互いに歩み寄る意志があってこそ、育っていくのだと思う。
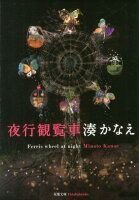
夜行観覧車
湊かなえ
本棚登録:348人
『セフネ』 たまたま生まれたひとつの縁が、生き方そのものを変えていく—— そんな出会いが、人生には時として訪れます。 ずっと探し求めていた何かと出会う瞬間、それは案外、好ましくない印象や違和感とともにやってくることもあります。だからこそ、その出会いの意味を見いだすには、時間と努力が必要で、その過程には、迷いや不安、時には悲しみや絶望すら伴います。 避けて通れない「嫌なこと」に直面し、乗り越えようとするなかで、これまでの価値観ややり方が通用しないことを痛感する。けれどその苦しみのなかで、自分の内側に何かが生まれ、感覚が変わり、視野が広がっていくのです。今まで受け入れられなかった価値や他者の在り方を、少しずつ受け入れられるようになったとき、人は静かに変化していきます。 その変化に気づき、心がふとやわらかくなる瞬間—— もしかしたら、それは「歓び」へとつながる第一歩なのかもしれません。 そしてその出会いこそが、人生を豊かにしてくれる“幸せの種”だったのだと、後から気づくものなのですね。

カフネ
阿部暁子
本棚登録:445人