ぴ
レビュー
使命感もなく、特に大きなエピソードもない。 筆者はちょっと偏屈だし、勿体無いと思うこともたくさんある。 でもそれがいい。気負わず自由に生きていきたい。
ネタバレを読む
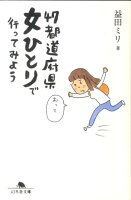
47都道府県女ひとりで行ってみよう
益田ミリ
本棚登録:108人
心の中で薄々わかっているけどついやってしまう人間の弱さについて書かれている本。 メンタルの調子が悪いときなどにたまに読み返すようにしたい。が、メンタルの調子が悪いときはこれを読んでも「なに当然のこと言ってるんだよ」と思ってしまうかも。笑

メンタルが強い人がやめた13の習慣
エイミー・モーリン/長澤 あかね
本棚登録:0人
ごく当たり前のことが書かれている本。 だが、このごく当たり前を無意識下でできている人間はほとんどいないのではないか。 自分自身強いバイアス(特に男女のバイアス)は持っていない人間だと思っていたが、持っていることを知らしめられた。 今の社会においては、全員必読の一冊なのでは。

あなたにもある無意識の偏見 アンコンシャスバイアス
北村 英哉
本棚登録:0人
嫉妬の恐ろしさを知った。 というのも、作者がいかに嫉妬という言葉であらゆるものを片付けているか垣間見てたからだ。 自分に向けられたマイナスの感情全てを嫉妬だと受け止めてしまうようで、自分の落ち度や反省点を見出そうとしていないように見受けられた。 嫉妬というものを過大に捉えてしまうと、自らの成長を阻むことになってしまうようだ。 妬む気持ちよりも、嫉妬されているという過剰な自尊心の方が恐ろしいのかもしれない。

嫉妬の正体
谷沢 永一
本棚登録:0人
強い感情は忘れません、というアンメットの言葉を思い出した。 痴呆にしても記憶喪失にしても知的障害にしても、一つひとつのできごとは覚えてられないかもしれないけれど、彼らの感情を大切にしたい。ほんの僅かでも、たとえ私の自己満足でも、たまには生き生きとした表情を見たい。 あなたが忘れてしまうであろうエピソードは、私が痴呆を病むまで覚えておくよ。
ネタバレを読む

痴呆を生きるということ
小澤 勲
本棚登録:0人
間違いなく考えさせられる内容ではあったが、醜悪な人種差別と公務員への外国人登用が同じレベル感で語られていることには違和感があった。 不当な外国人差別が許されないことは言うまでもないが、テロ等の国防リスクを考えたら多少の制限が生じることは致し方ないことではないか。 議論の余地があることとないことを一緒くたにしている印象を抱いた。

ヘイト・スピーチとは何か
師岡康子
本棚登録:0人
自分が1年半考えて結論が出てこなかった「彼らはなぜ生きているのか」という問いに対しての作者が考えた答えを読んで、これは本当に向き合ってきた人の考えだと感じた。障がい者にここまで寄り添ってくれるエリートがこの世にいることは救いだ。 「この子らに世の光を」ではなく、「この子らを世の光に」。忌避されがちな障がい者にとって果てしなく遠い理想だとは思うが、その気持ちを持って障がい者と向き合っていたい。

重い障害を生きるということ
高谷 清
本棚登録:0人
・自己研鑽の時間は先に押さえておく ・目標からバックキャスト(月単位の予定管理) ・リミットを設けた方が集中力が増す ・やることを時間割にしてルーティン化した方が考えなくて良いので楽 ・知能労働は終わりがない。8割で良いものは8割で ・仕事の段取り設定や革命を起こすための作業(システム化など)には時間をかける ・雑誌などは目次を見て自分に必要なところだけ読んでいる

レバレッジ時間術
本田直之
本棚登録:0人
各宗教の基礎的な背景や置かれた状況が説明されている。 これまで一種のアングラジャンルとして見ていた新宗教について、体系立った理解ができる。 これは20年近く前の本なので、さらに最新の状況についても調べてみよう思う。

日本の10大新宗教
島田裕巳
本棚登録:0人
言ってはいけないの直後に読んでよかった。 ささやかではあるが、希望がないわけではない。

ケーキの切れない非行少年たち
宮口幸治
本棚登録:463人
1章とそれ以降のクオリティに差があったように感じる。 1章はある程度それらしい根拠があり、説得力が備わっていた。対して2章以降は、「〜だろう」という根拠に乏しい話の展開が多く、あまり納得できなかった。

言ってはいけない
橘玲
本棚登録:0人
湿っぽい、というネットで見た感想がぴったり。 劇的なことは(心中以外)ほとんど起こらず、 ただ淡々とホテルでの描写が続く。 ヌード写真を撮るカップルの彼女は、撮影が嫌でも結局笑うことしかできない。 オーナーの娘は業者の男を誘うが成功しない。 夫婦のひさびさの2人の時間を過ごせた話はいい話だったが、その後そのローヤルは潰れてしまう。 そして何より、妻に不倫された教師と親に捨てられた女子高生は心中してしまう。 唯一の救いはローヤルで働いていた清掃の女性だろうか。旦那が迎えに来てくれるが、それでもきっと無職の旦那を支えなければいけない彼女の日々はこれからも苦労の連続だろう。 すごく面白いか、と言われると分からないけど すぐに最後まで読んでしまうくらい引き込まれたことは間違いない。 私も面白くはなくとも最後まで読みたくなるような文章を書けるようになりたいし、人としてもそういう不思議な魅力が欲しい。

ホテルローヤル
桜木紫乃
本棚登録:0人
どこまで現実のディズニーランドでどこからが架空の物語なのか分からなかった。すごい! 嘘をつくときは事実を織り交ぜながら、と言うのは本当なのだなと学べた。 続編も読みたい

ミッキーマウスの憂鬱
松岡圭祐
本棚登録:143人