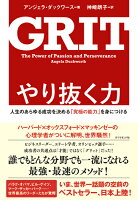匿名ユーザー
レビュー
思考の整理学』は、「グライダー人間」(受け身の思考)から「飛行機人間」(自力で飛び回る思考)へ転換し、創造的な思考を生み出すための方法論を説く本で、「寝かせる」「忘れる」「書き出す」といった行動を通じて、アイデアを発酵・熟成させ、本質的な思考を整理することを提唱しています。情報過多の現代において、知識を詰め込むだけでなく、必要な情報を取捨選択し、思考を「発酵」させるプロセスが重要だと強調されています。 主な要点 グライダー人間から飛行機人間へ: 学校教育で育つ「グライダー人間」(受け身)ではなく、自ら考え、飛び回る「飛行機人間」を目指すべきと説きます。 「寝かせる」ことの重要性(発酵): アイデアや問題は、すぐに解決しようとせず、一旦「寝かせる」ことで、無意識下で情報が整理され、良質なひらめきが生まれます(発酵)。 「見つめる鍋は煮えない」というように、集中しすぎず、適度に忘れることも大切です。 「忘れる」ことの効用(捨てる): 不要な情報を忘れることで、頭が整理され、新しいアイデアを取り込む余地が生まれます。情報の取捨選択と忘却が創造性を高めます。 「書き出す」ことの効用(メタ化): 思いついたことを手帖などに気軽に書き出し(一次情報)、それらをノート半ページなどにまとめ直す(メタ化)ことで、思考の構造が見えてきます。 さらに発展させたい思考は、専用の「メタノート」にまとめ、関係性を見直します。 プラス思考と人間関係: 行き詰まった時は、「きっとうまくいく」と自分に言い聞かせ、肯定的な態度でいることが思考を活性化させます。自分を認めてくれる人と付き合うことも重要です。 まとめ 『思考の整理学』は、情報収集だけでなく、それを「寝かせ」「忘れる」ことで「発酵」させ、「書き出す」ことで「メタ化」するという具体的なプロセスを通じて、情報に流されず、自分ならではの創造的な思考を生み出すための実践的な指南書です。

新版 思考の整理学
外山滋比古
本棚登録:0人
人を喜ばせるや助けるため 人が欲しがっているものを先取りする その日の最後に頑張った自分を褒める 何かをやめて別のものを得る 決めたことを続けるには具体的行動を取る 自分が1番得意なことを人に聞く 自分の苦手なことを人に聞く 運が良いと口に出して言う 事前に周到に準備をする 身近にいる1番大事な人を喜ばせる 人のいいところを見つけ褒め自尊心を高める 人の長所を盗む、パクる 自分が楽しめる仕事を見つける やらずに後悔していることを今日から始める 人の成功をサポートする 毎日感謝をする

夢をかなえるゾウ1
水野敬也
本棚登録:199人
宗教と経営の共通点: 宗教と経営には、理念への共感、組織の結束、目標達成へのコミットメントなど、共通する要素が多く存在します。例えば、キリスト教やイスラム教といった世界宗教は、信者をまとめ、社会に大きな影響を与える組織として、その原理を学ぶことで、企業組織の運営に役立てることができます。 理念の重要性: 宗教が教義や教祖を信じることで組織をまとめ、社会に広がっていくように、企業も理念を社員が心から信じ、行動することで、業績を伸ばし、社会に貢献することができます。逆に、理念が形骸化していると、組織は弱体化し、成果を上げることが難しくなります。 「腹落ち」の重要性:センスメイキング 変化の激しい現代社会では、社員が理念に「腹落ち」することが、より重要になっています。宗教が、信者の「腹落ち」を促すように、企業も社員の共感を呼ぶ理念を掲げ、それを浸透させることが、組織を強くし、イノベーションを加速させる原動力となります。 イノベーションと宗教: イノベーションを起こすためには、既存の枠にとらわれない発想や、新しい価値観を創造する必要があります。宗教が、既存の価値観を否定し、新しい世界観を提示することで、人々に影響を与えてきたように、企業も宗教的な視点を取り入れることで、イノベーションを促進できる可能性があります。 組織のモデルとしての宗教: キリスト教やイスラム教のような世界宗教は、強固な組織構造と、信者を惹きつける理念を持っています。これらの宗教の組織構造や理念を学ぶことで、現代の企業が、ティール組織のような、より柔軟で自律的な組織を構築するためのヒントが得られるでしょう。

宗教を学べば経営がわかる
池上 彰/入山 章栄
本棚登録:0人
ホワイトカラー層の縮小 ・AIで単純業務やジェネラリストは不要に ・「意思決定しないホ◆ホワイトカラー」は淘汰 ◆「選択と集中」が企業存続の鍵 ・競争力のある領域に資源を集中すべき ・不要なホワイトカラーを削減し、生産性向上 ◆個人も「専門性」が必要 ・ジェネラリストより専門職が求められる ◆アドバンスド・エッセンシャルワーカーの台頭 ・AIに代替されにくい高度技能労働者が重要 ◆雇用システムの変革 ・年功序列を廃し、ジョブ型雇用へ移行 ◆企業・個人ともに変革が急務 ・企業はデジタル化、個人はスキル向上を

ホワイトカラー消滅
冨山 和彦
本棚登録:0人
2024/06/29 「株式市場原論」丸木強アクティビスト 東大法 野村證券 村上ファンドを経て、ユニークな経歴・本質的 日本の長期低迷は「株価低迷」に表れている(p4) 「企業価値の向上」こそが本質的命題! 現代日本企業の経営論として必読の書 1.経営=資本効率を高めつつ長期的成長を実現する それをチェックし、成績不芳な経営・経営者を糾すのが資本市場 「PBR<1の経営は落第キャンペーン」が成功しつつある その前から、ROE10% ガバナンスコード 人的資本など 2.PBR<1のインパクト→日本の企業経営は変わる⇒株価上昇へ ①経営・経営者の評価 ②資本効率向上への意識と行動、実績評価 ③株主が最優先 自己資本=過剰な内部留保を還元 ④M&Aにポジティブイメージ 防衛策の否定 ⑤政策投資の否定 資産の効率低下 ガバナンスの希薄化 ⑥役員人事の透明化・実績スキルベース 天下りの否定 3.経営者は企業価値を高めることが責務 それができないorもっとできる経営者へ譲らなければならない ex セブンイレブン そごう・西武の売却 「M&A」が企業を流動化し、価値を高める方向へ進む それにより従業員の将来はよりハッピーとなる 社会も 4.経営者の経営スキル ROIC>WACC 投下資本利益率Return on Invested Capital 株主資本コスト=加重平均資本コストWeighted Average Cost of Capital 5.経営者にたかる「寄生虫」多くの専門家・管理業務過剰 日本は「管理過剰」特に官僚の関与が異常「業法」 市場経済の根本である「価格」は公定価格か届け出価格の多さ それに加えて「専門家の士族」弁護士・公認会計士 社外取締役として多くは寄生虫 議事録で貢献しているのか? 彼らはかっての「与党総会屋」と同じ 不特定多数の株主やアクティビストに介入されぬ為にはマネジメントバイアウトMBOも一手:経営陣が一般株主から株を買い取り、自社買収して上場廃止、非上場企業になる。大正製薬/ベネッセ/シダックス ◆PBR1倍超えの為に株主還元増やす❶自社株買い。発行済株式100株のうち10株を自ら買い取り90株にすれば、1株あたり利益は約1割増える❷配当金増やす増配。一度増やすとなかなか元に戻しにくいので株主還元持続 ◆買収防衛策は当社は割安と宣言してる様なもの ◆株式公開買付けTOB:不特定多数の株主から株式を買い集める買収手法 金融庁スチュワードシップコード:機関投資家は投資先企業との対話通じて持続的成長促し投資リターン最大化目指すべし。金融庁&東京証券取引所コーポレートガバナンスコード:上場企業の企業統治原則。経営の透明性高め、持続可能な成長や企業価値向上すべし◆ESGのグリーンウォッシュ、ガバナンスやスキルマトリクスウォッシュいい加減を見逃さない ◆アクティビスト対策の相談に乗る弁護士やコンサルは企業の株主価値向上を考えず現状肯定するだけの取締役会意見や容易に達成できる無意味な中計の原案作成。企業から報酬もらうので。 株主還元も投資もせず無駄に自己資本を溜め込むと分母大きくなり 低い自己資本利益率ROE。アクティビストは投資家から資金を募り、特定企業の株を一定買い進めて存在感を高め(上場企業の株3%持てば大株主)経営改善提案を繰り返していく。株主総会での株主提案や株主代表訴訟、敵対的買収、社外取就任など派手な活動は一部。賛成過半数で一度に勝つこと目指さず、まず20%でも主張知ってもらう。事業内容よりもガバナンスのあり方や財務状況に口出す ◆IR(株主・投資家に対する経営戦略・財務状況等の広報活動)しない上場企業は株主軽視

「モノ言う株主」の株式市場原論
丸木強
本棚登録:0人
分析に論理がない。 歯抜けの説明だ 金額で物事を捉えていない。事業の共通の尺度は金額しかない。 資金が減っている。 番頭役の務めを果たせ。 松下電器の経理は経営に参加するという重大な 職責を持っている。経理という職能によって自ら経営を行っていると言っていい 。これを経営 経理 という 。経営経理 つまり 経営に役立つ経理 、経営組織の中で神経系統としての役割を果たす というわけである CFOには 4つの側面がある 1.対 トップ 参謀 番頭 役 としてのCFO 客観的な見通しに基づき トップに進言 時には 苦言 2.対株主 投資家等 社外との媒介役 的確に 情報開示 市場の見方を経営に活かす 3.対従業員 戦略の仕掛け作り プロデューサーの役割 4.対経理部門 経営管理のためにリーダーシップを発揮 チーフ フォーカスオフィサーとしての役割 様々な課題の中で優先順位をつけ やるべきことに焦点を当てる 役割 本質的 中長期的 多面的 この3つを いつも 念頭に置け 10÷3その心は余った1を相手にあげなさい 幸福とは 過去に思い出がたくさんあること 現在に打ち込めることがあること 未来に夢と希望があること この泥があればこそ 咲け蓮の花 数字の裏に人あり物あり 事業部のトップは製品の部品の原価 まで把握するべし 研究開発の中身も把握しろ ストーリーが大切 突き詰めた分析を 本質的な課題を掘り下げて先手を打つ 繋がりが さっぱりわからん 分析のまとめに 論理がない 歯抜けの説明になっている いいとこどりで良いことばかり言わずに今は 問題点を明確にすることが大事だ 本当に増やすべき コストと増やさなくても良かった コストを区別して検討すべきだ 資金が減っている経営が悪くなっているのに良くなっていると錯覚しているのではないか これでは 番頭 役とは言えない 最も警戒すべき現象の一つだ 番頭役の務めはポイントをきちんと捉えて指摘すること そこをずらしてはいけない 仕方がない やむを得ないで物事を進めすぎていないか それを先行投資という美辞麗句で捉えてしまっている もっと早く手を打てば ここまでの資金の悪化はなかった 感性を磨き 自分を見つめる IR を有効なものにするためのポイント 1.トップの関与 2.全社的な IR 体制の整備 3.自分自身を磨くこと 出世のコツは 何ですか 1つは愛嬌があること もう一つは仕事を好きになること 愛嬌とは お客様を意識した自分であれ ということだろう お客様の視点を忘れてはもはや 仕事ではない そして自分の仕事に惚れ込むこと それこそ大事な心意であると 幸之助さんは言う それだけではなく患難を喜んでいる なぜなら 患難は忍耐を生み出し 忍耐は練達を生み出し 練達は希望を生み出すことを知っているからである そして希望は失望に終わることはない

CFO魂の鍛え方
川上 徹也
本棚登録:0人
人間関係が豊かだと幸せになりやすい お金があれば幸せになれるわけではないが不幸を避けることはできる ノーベル経済学賞を受賞した 心理学者 ダニエル カーネマンは年収800万円を上限に 幸福度が高止まりすると言っている 50歳の時の人間関係がいいと 80歳の時のに健康状態も良くなる 遺伝はどうにもできないが人間関係は自分次第でどうにかなる 孤独は痛みである 実際に 孤独感があると痛みに敏感になり 免疫力が弱まり脳機能が低下し 睡眠の質が悪くなり疲労感 や イライラが増す ふれあいは麻酔薬のように痛みを和らげる効果がある スクロールをやめて相手に注意を向けること 話しかけないよりも 話しかけた方がいい 人と人との関係はほったらかしでは育たない 仕事をしすぎて 人間関係をおろそかにしないこと 引退 生活が充実している人は職場以外で新しい仲間を見つけていた 仲間がいなくても老後に何でもいいから仕事をすることも大切 人生を支えてくれる10人の人間関係を把握する 他者との交流の頻度と質こそ幸福のポイント 他人に誠実な関心を向ける 人に好かれる 6 原則 1 誠実な関心を寄せる 2 笑顔を忘れない 3名前を覚える 4 聞き手に回る 5 関心のありかを見抜く 6心から褒める デールカーネギ 人を動かす

グッド・ライフ
ロバート・ウォールディンガー/マーク・シュルツ
本棚登録:0人
えー本 自らの立ち位置に悩みがちなコンサルタントの役割を「参謀」と明確に定義 -多くのコンサルタントは「経営に関われる」との思いからこの仕事に就くが、結局経営の決定権は無いという点に悩んだりもする。 -この点に対し、コンサルタントは経営「参謀」なのである、というのが(明示はしていないのだが)非常に分かりやすく伝わってくる -参謀として、「課題を設定する」、「経営者を刺激する」、「適切な意思決定を促進する」の3つを行うことが価値なのである、ということが理解できる ●経営者から反発を引き出さなくては意味がない、との繰り返しの指摘 -参謀としては、「いいね」「この方向性で」という経営者からの言葉をポジティブに受け取ってしまいがち -しかし、そもそも曖昧なことが多い経営者の課題設定を、より本質化・明確化していくには、十分な議論が必要であり、上記のような反応はそれを満たしてくれない -むしろ、反発を引き出し、「経営層の懸念点」を浮き彫りにすることが、議論の活性化にとって重要である 課題を出した経営者は、実は何をどのレベルで議論すればいいのか分からず、まずは課題と論点から明らかにしてほしいと思っていることが多い ・たとえ経営層でも、自分たちだけで簡単に答えを出せる時代ではなくなっている ・問いのディシジョンツリーを、先回りして作っておく ・きれいな材料に基づく浅い問いかけでは潜在意識(欲求、葛藤、価値観、判断基準、存在意義、アイデンティティ)に問いかけられない。深い問いかけが必要。 ・何が経営層に響くかの検討にはセンス、イマジネーション、直感力が必要。はっとするものは、反論を言いたくなるようなアイディアであり、小さくまとまったものではない。相手を怒らせることを恐れない。決して横柄になってはいけないが。 ・何かあればすぐに議論できるディスカッションパートナーを持つ ・「自分を道具として使ってでも会社をこう変えたい」と強く信じられる将来像があるか ・他人の意見を素直にいいなと思えるセンスは重要 ・何らかの方法で経営陣と議論するように、ブレークスルーを起こす ・自分で見えないスコープで論点を探す。自分が見ている世界が全てではないと自覚する。いろいろな人に話を聞く。少数意見やマイノリティの視点に大きなヒントが潜むケースは多い。 ・経営層と同じ視点、視野、視座で物事を捉え、相手の頭の中をイメージする力を持つことが重要。高いクリエイティビティやイマジネーションが求められる ・担当の時間から、リーダーの時間に体内時計を入れ替える→経営層にとってNewなもの、面白いものを導出する分析作業は初期段階で早めに手掛ける ・チームマネジメント:自分ならこれぐらい出来たはず、と思う工数の7掛けくらいでみておく ・良いコンテンツ=それをきっかけに議論が広がっていくもの ・5枚のキースライドと、それを支える20枚のボディ ・浅い理解にとどまりそうなポイントには勇気をもって切り込む ・目の前で起こっている現象について、「実は一過性のブームではないか」と疑うセンスは必要 ・変化を新たなチャレンジと考えてワクワクして臨む ・プロジェクトの節目でリバースエンジニアリングをすることはとても重要。成功パターンを頭の中で築いていく ・テーマごとにネットワークを持ち、相談の頻度と成果をトラッキングする。また、気楽な人間関係だけに甘んじていないかチェックする ・自分のホームグラウンドを持ち、そこからのアナロジーを考える ・人の話に被せない。上司が言ったことは一度飲み込んで咀嚼してから返答する ・4つの心の病:自惚れ、おごり、甘え、マンネリ ・議論に対立構造が生まれたときには抽象化してみる ・おじさんの言語を学ぶべし ・出会いの運を機会と思い、機会から経験を積み、経験から学ぶループを回す

プロフェッショナル経営参謀
杉田 浩章
本棚登録:0人