エヌ氏(公式)
レビュー
読んでないけどメルカリ行き。
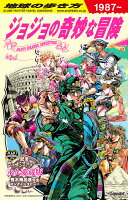
地球の歩き方 JOJO ジョジョの奇妙な冒険
地球の歩き方編集室
本棚登録:0人
読んでないけど、メルカリ行き。

地球の歩き方 ムー
地球の歩き方編集室
本棚登録:15人
甘えるな。ひたすら泥臭く続けろ。
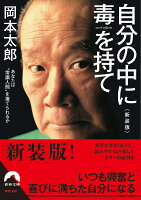
自分の中に毒を持て<新装版>
岡本太郎
本棚登録:0人
量子コンピュータの実用化はまだ先。 量子コンピュータは、量子力学に基づく。 量子力学は普通の物理法則とは異なる。 原子を一個飛ばしたところ、波のような動きをする。 量子力学の発達まで量子コンピュータの実用化はない。 Googleの量子コンが現行コンより速いというのは、特定の条件下におけるもの。 Googleのマーケティングにすぎない。

量子コンピュータが本当にわかる! - 第一線開発者がやさしく明かすしくみと可能性
武田俊太郎
本棚登録:0人
意味がわからない… 詩を読むといいって
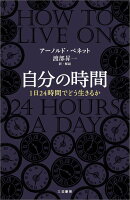
自分の時間
アーノルド・ベネット/渡部昇一
本棚登録:0人
メタバースでどうマネタイズするのかがわからなかった

メタバースビジネス覇権戦争
新 清士
本棚登録:0人
雑学本。幹がない俺には意味がない。
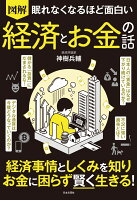
眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話
神樹兵輔
本棚登録:0人
クソ本。 ただの仕事の広告と感想。 データなどなし。

日本のシン富裕層
大森健史
本棚登録:0人
ウクライナ戦争は、アメリカのせい。 アメリカは常に戦争をし続けている。 アメリカが悪だ。 ウクライナは個人主義、ロシアは家族主義。 文化が違う。 そもそもウクライナは3つに別れてて、国家といえる状態だったのか。 ロシアとフランスはこの戦争に後ろ向き。 アメリカイギリスだけ前向き。 ロシアの解体が目的。 アメリカの目的がわからん。 費用対コストあってる?

第三次世界大戦はもう始まっている
エマニュエル·トッド
本棚登録:0人
インフレは、需要と供給のマッチング 従来は、需要が強くなることに対して、中央銀行、政府が金融政策等を行なってきた。 今のインフレは、ウクライナ戦争の前から始まっている。 需要側の問題ではなく、供給側の問題。 サプライチェーンの崩壊によるもの。 パウエルの金融引き締めは、処方箋の一つであるが、それが確実に効くかはわからん。 日本は、デフレと急性のインフレ。 たぶん、企業が調整弁になってる。 政府とか日銀が信用できないからじゃないかな。

世界インフレの謎
渡辺 努
本棚登録:0人
33冊目 最高の時短 所要時間:1時間 目 次:第1章 最高の目標設定 1 「やりたいことが見つからない」はただの逃げ 2 「今日何をやるか」ではなく「どう生きるか」 3 「やみくもな努力」は「挫折のもと」 4 成功への「最短ルート」は自分で見つけるものではなく「人に聞くもの」 5 まず「結果」でなく「チャレンジ」の定量目標を設定する 6 「一度決めたことをやり通す」ほど無駄な事はない 第2章 「努力しない」勇気 1 目標達成は「努力」ではない 2 「石の上にも3年」の時代は終わった 3 フィードバックを得ることが「努力しない」秘訣 4 効果が出ないものはすぐに切り捨てる 5 「人に頼む」「人に任せる」が正義の時代 6 尊敬できる人、好きな人から学ぶと楽しい 7 「強烈な個性」が「爆発的な成果」を生み出す 8 「勝ち負け」という概念から外れてみる 9 「苦労する人生をわざわざ選択しない」と覚悟を決める 第3章 「先を読む力」を鍛える 1 「なぜ?」の深掘りを最低7回は行う 2 「自分だけは正しい」という概念は全て捨てる 3 「先読み思考」と「逆算思考」で未来を見通す 4 考えずに「シンプル」にやる 5 作業が終わっていなくても提出する練習 第4章 「1週間に14時間」だけ働く 1 仕事の速い人と1週間、生活をともにする 2 「タスクのレベル」で時間を使い分ける 3 働く時間を決める 4 常識は時短における最大の敵である 5 メモは取らなくていい 6 決断は「情報量」がカギ 7 スマホだけで仕事を完結させる 8 1日にやる「大事な3つのこと」を決める 9 やりたくない仕事を最速で片付ける技術 第5章 誰からも時間を奪われていけない 1 24時間の時間割をつくる 2 「断る力」を一刻も早く身につける 3 稼ぐ金額は「かけた時間」に比例しない 4 集中力は才能ではなく訓練で身につく 5 自分以外の時間を有効活用する 6 自分が責任を持つ空間を自分で定義する 感 想:1日2時間だけ仕事するを実践してみる

お金と時間の悩みが消えてなくなる 最高の時短
米山 彩香
本棚登録:0人
32冊目 運動脳 所要時間:1時間 目 次:第1章 現代人はほとんど原始人 1 運動で脳は「物理的」に変えられる 2 100兆もの「脳内連携」をフル稼働させる 3 大人の脳が持つ可逆性ー柔軟で変形する 第2章 脳から「ストレス」を取り払う 1 頭を鈍らせる「見えない敵」 2 運動でストレス物質「コルチゾール」をコントロール 3 世界のストレス研究がこぞって「運動の効果」を発見中 ー運動がおそらく最も優れた解毒剤 4 敵になるストレス、味方になるストレス 5 賢いストレス・不安を解消する 第3章 「集中力」を取り戻せ! 1 思考を1点に絞る「フォーカス・メカニズム」 2 集中物質「ドーパミン」を総動員する 3 「注意散漫」の最新サイエンス 4 自分をコントロールして最後までやり抜く 第4章 うつ・モチベーションの科学 1 意欲が湧かないのはなぜ? 2 最強脳物質「BDNF」を分泌する 3 「ランナーズハイ」は実在する 第5章 「記憶力」を極限まで高める 1 1日10万の細が死滅 2 脳細胞の復活劇 第6章 頭の中から「アイディア」を取り出す 1 アイディアの科学 2 アイディアが歩き出す 3 「創造の発信源」を突き止め刺激する 第7章 「学力」を伸ばす 1 学力と連動の絶対的な関係 2 IQを高める 第8章 健康脳 1 「脳の老化」をストップする方法 2 健康な頭脳が「健康寿命」を長くする 3 科学が示す「現時点で最新の結論」 感 想:一日30〜45分ランニングしろ

2030 半導体の地政学
太田 泰彦
本棚登録:0人
所要時間:1時間 目 次:第1章 現代人はほとんど原始人 1 運動で脳は「物理的」に変えられる 2 100兆もの「脳内連携」をフル稼働させる 3 大人の脳が持つ可逆性ー柔軟で変形する 第2章 脳から「ストレス」を取り払う 1 頭を鈍らせる「見えない敵」 2 運動でストレス物質「コルチゾール」をコントロール 3 世界のストレス研究がこぞって「運動の効果」を発見中 ー運動がおそらく最も優れた解毒剤 4 敵になるストレス、味方になるストレス 5 賢いストレス・不安を解消する 第3章 「集中力」を取り戻せ! 1 思考を1点に絞る「フォーカス・メカニズム」 2 集中物質「ドーパミン」を総動員する 3 「注意散漫」の最新サイエンス 4 自分をコントロールして最後までやり抜く 第4章 うつ・モチベーションの科学 1 意欲が湧かないのはなぜ? 2 最強脳物質「BDNF」を分泌する 3 「ランナーズハイ」は実在する 第5章 「記憶力」を極限まで高める 1 1日10万の細が死滅 2 脳細胞の復活劇 第6章 頭の中から「アイディア」を取り出す 1 アイディアの科学 2 アイディアが歩き出す 3 「創造の発信源」を突き止め刺激する 第7章 「学力」を伸ばす 1 学力と連動の絶対的な関係 2 IQを高める 第8章 健康脳 1 「脳の老化」をストップする方法 2 健康な頭脳が「健康寿命」を長くする 3 科学が示す「現時点で最新の結論」 感 想:一日30〜45分ランニングしろ
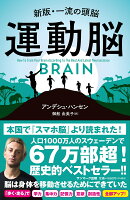
運動脳
アンデシュ・ハンセン/御舩 由美子
本棚登録:0人
国語を数学的に思考すると良い 量が質を作る アウトプットするとこで読解力の意識も高まる

大人に必要な読解力が正しく身につく本
吉田 裕子
本棚登録:0人
所要時間:4時間 目 次:第1章 これがAIだ 1 今、社会でAIが大活躍している 2 AIに仕事を奪われる 3 AIはとても賢いコンピューター 4 AIは2度のブームと冬の時代を経て開花した 5 AIの新時代を拓いたディープラーニング 第2章 AIの革新的技術 ディープラーニング 1 AIに知能をもたらす「機械学習」と「ディープラーニング」 2 AIは自ら学習して賢くなる 3 ディープラーニングは、脳の神経細胞がお手本 4 人が脳がものを認識する仕組み 5 AIが画像を認識する仕組みは、人間の脳ほぼ同じ 6 AIは情報ごとに「重み」をつける 7 AIは、ものの情報を自分で見つけ出す 8 耳に長い猫を猫と判定させるには 9 AIは人間よりも賢くなる 第3章 人間社会を一新するAI 1 AIは標識の識別が得意 2 自動運転車のレベルは6段階 3 AIの思考回路は人間では解読できない 4 自動運転車も「認知・判断・操作」をしている 5 自動運転車の認知能力は自律型と協調型の2種類 6 自律型の自動運転は既に可能?! 7 自動運転車は渋滞しない 8 眠気感知で居眠り運転を撲滅 9 自動運転のバスやタクシーが始動 10 AIは美容室の予約をしてくれる 11 AIは意味から音声を推測する 12 音声アシスタントAIは、会話から使える機能を探る 13 おもてなしのできるAI 14 ディープラーニングで、翻訳制度がアップ 15 AIは行間が読めない 16 どんな環境でも言語でもOKなAIは実現する? 17 会話ができるAIの壁は常識の取得 18 急速に進歩する医療AI 19 AIでがんを見つけ出せ 20 AIが脳の画像から異常を発見 21 医療用AIの学習は、量も質も大事 22 話し方の特徴から精神疾患の有無を審査 23 手術の腕前をAIが客観的に審査 24 患者に適当ながん治療を提案してくれるAI 25 医師と連携する「AIドクター」 26 薬に使えそうな物質を提案「創薬AI」 27 将棋・囲碁・チェスの最強AI「アルファゼロ」 28 サッカーの戦術を分析「ピッチブレイン」 29 材料の開発にAIが活躍 30 高速道路のひび割れを点検するAI 31 AIが隠れた系外惑星を発見 第4章 AIの未来 1 AIが騙されても人は気がつけない 2 AIのウソ、ディープフェイク 3 AIに求められる公平性 4 「データの活用」と「プライバシーの保護」 5 AIは「適当」がわからない 6 AIは言葉の「本当の意味」を理解していない 7 AIの不安要素「不透明性」と「制御不能性」 8 AIに「倫理観」を持たせるべきか 9 AIは「創造性」を獲得できるのか 10 AIが小説家デビュー 11 AIの進化を予測する 12 「何でもできるAI」とは 13 「何でもできるAI」は作れるのか 14 AIが人類を越える「シンギュラリティ」が到来 15 人はAIの暴走を止められるのか 感 想:ディープラーニングと機械学習の違い 概念的に、機械学習>ディープラーニング 機械学習は、プログラムが、自律的に、カテゴライズする。 ディープラーニング(深層学習)は、より複雑な特徴を理解する事ができる。ディープラーニングは、人間の脳、すなわち、例えばいちごの場合、認識(目)→神経(神経において、情報に重み付けをする)(階層1:色、階層2:縦線・横線、階層3:縦線や横線んどの構造を複合化した特徴を認識)→いちごというように、人間の脳の認識を模して、多層的に認識させることで、いちごをカテゴライズする。 AIは「創造性」をもてるか、それは人類自身が、「創造性」を理解しなければならない。人類が「良い」と評価するものの基準や特徴をAIが理解することで、それを「創造性」とするならば、創造性を持つことができると言える。 AIの進化 能力1 画像を正確に見分けられる 能力2 複数の感覚データを使って特徴を掴む 能力3 動作に関する概念を獲得する 能力4 行動を通じた抽象的な概念を獲得する 能力5 言葉を理解する 能力6 文字や言葉を使って知識や常識を獲得する 2020年前半に、能力3まで獲得 2020年後半に、能力6まで獲得 特化型AIから汎用型AIへ 特化型AI:設計した人間が想定した特定の課題に特化したAI 汎用型AI:想定されていない、未知の課題に対応できるAI 汎用型AIは人間の脳全体の構造を真似た次世代AI 全脳エミュレーション、全脳アーキテクチャ 2030年 汎用型AIが開発 レイ・カールワイツ博士 2029年 人工知能があらゆる分野で人間の能力を越える 2030年代 人間の脳に、脳のニューロンを刺激するチップが埋め込まれる。人間と脳とインターネットが直接接続させる。血球サイズの微小なロボットが人体内に入り、免疫システムを補助する。 2045年 脳と人工知能が融合し、人類の知能が10億倍以上に拡張。知能向上から生まれる技術や社会の変化が予測不可能な状態に。シンギュラリティが発生。

東京⼤学の先⽣伝授 ⽂系のためのめっちゃやさしい ⼈⼯知能
松原 仁
本棚登録:0人




