りんな
レビュー
ゆうちゃんに借りた本 好きなことを見つける→ 好きなことでは熱意があるから、ツイている状態が続く→ 気づいたらお金が増えている このサイクルを作り出せると、 お金を稼ぐ+自由な時間を作りだせる

愛蔵版 ユダヤ人大富豪の教え
本田 健
本棚登録:0人
行動経済学の本 完読するのに2月ほどかかってしまったが、前に読んだ2冊と概ね内容はカバーされている。この本は、お金のことに関するトピックがあり、保険の選び方などベンキョになることがあった

NUDGE 実践 行動経済学 完全版
リチャード.セイラー/キャス.サンスティーン
本棚登録:0人
ここ最近読んだ本で、一番面白かった 人間がいかに不合理に動いているかを学ぶことができた 個人的に面白かったのは、性的興奮は人の理性を著しく低下させることだ。性的興奮をイメージして選択した場合と実際に性的興奮状態で選択した結果は全く異なる。不貞行為など起こさないためには、まずはそういう状況を作らないことだ また無料と書かれていると、人は遠慮することがわかった。同じチョコを無料と一円で配る場合、1円の方がたくさん配られた。無料であると社会規範が適応され遠慮するが、値段が設定されると市場規範になるためビジネスライクに安くたくさん買うという心理が働く。 また彼女とのデートでデート代を話題に挙げると、市場規範に頭が切り替わってしまうため関係を保つためにも良くない。自分の経験でもそれは感じた。 とても面白かったため、もう一度読みたい
ネタバレを読む
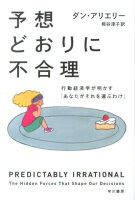
予想どおりに不合理 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」
ダン·アリエリー/熊谷 淳子
本棚登録:0人
失敗学という新しい学問の提唱 本書や失敗図鑑などを読んでいたこと、自分が末っ子で年上兄弟の失敗を見て育ったことから、自分は失敗から学ぶことが好きなのかもしれないと思った 失敗を伝えるには、単に事実だけでなく当時の心情など立体的な情報を伝承しないと、リアリティがない情報として形骸化してしまう (日記に天気など、その記憶に関連する情報を追記することも、当時をイメージして、思い出させるという意味があると思う) 失敗をしないためには、イメージトレーニングが大事である(本書では別の文言)。仮想して、対策するなどをなんども繰り返すことで無駄な失敗はしないで済む。学生時代に部活動で試合前にイメージトレーニングするのは、良いイメージをつけるため、と思っていたが、今思えばこういう場合はこうしようなど無意識に仮説を立てて検証していたと気がついた。 また失敗が多い業界は、技術が成熟していること、コストカットが要求されるような企業である。日本ではほとんどの企業が当てはまるのでは,,, 自分の所属する会社ではトラブルシューティングを行なっているが、失敗例がすぐに参照できるかと言われるとそうではないと思う。システムを要確認されたい。
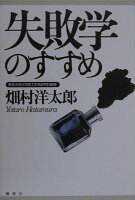
失敗学のすすめ
畑村洋太郎
本棚登録:0人
もりちゃんに教えてもらって読んだが、面白くなかった 一流、二流、三流と書いてあるが、しっくり来ない スタイルはそれぞれだと思うし、元々三流の人は無理して一流の真似をしても、空回りして、意識だけ一流という鼻につく人間になってしまいそう
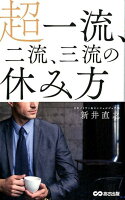
超一流、二流、三流の休み方
新井直之
本棚登録:0人
ねずみ講が禁止されている理由が知れて面白かった そのほかの内容は軒並み おおよそ知っているが自分への注意喚起 声かけられるのも若者の特権 おっさんには関係なし

ルポ 脱法マルチ
小鍜冶 孝志
本棚登録:0人
イタリアの食と人々の生活を書き記している。晩御飯には数種類のチーズが出ないとダメ、みんな昼ごはんは家に帰ってコース料理を食べてまた働くなど、30年近く前の本だから現在までどのくらいこの文化が残っているかは定かではないが、イタリアの庶民の暮らしについて知れたのでとても面白かった。日本語が上品で、読み心地もよかった
ネタバレを読む

イタリアの陽気な晩餐会
アッカーメ・森下京子
本棚登録:0人
バックパッカーの話 どの国の話も面白い

深夜特急3
沢木 耕太郎
本棚登録:0人
行動経済学=マーケティングの本 確率が35%を境に、35%以下だと確率を過大評価し、35%以上だと確率を過小評価するプロテクト理論は面白かった

サクッとわかる ビジネス教養 行動経済学
阿部 誠
本棚登録:0人
プラントの溶接工の話 ライ麦畑でつかまえてを彷彿とさせる厨二病主人公とした小説。自分にしか出来ない溶接があると傲慢な主人公が、他人には出来ない仕事で誇り高く持っているかと思いきや、実は卑下しており、他人から馬鹿にされると激昂してしまう。歳は40だけど主人公のムーブは中学生さながら。最後の50ページ付近で出てくる牧野との会話で、牧野のセリフがないことで、相手を考えることもなく、自分のことにしか目を向けていないことがよく物語っている。 面白かった
ネタバレを読む

我が手の太陽
石田 夏穂
本棚登録:0人
官僚がかいた暴露本。日本の電力会社と政府のズブズブの裏社会の仕組みについて、赤裸々に書かれている。 電力会社は、ベンダーと高値で取引をする代わりに、ベンダー利益の5%程度を電力会社所有の法人にプールさせている。そのプール金を使って政治家との繋がり、政府と電力会社が良いような仕組みを築き上げている。この際技術的安全性はどうでも良いみたいだ。反対勢力は、否が応でも排除し、自分達の懐を肥やす。 石油系の会社にいる限り、技術的安全性を担保することは必須であることは間違い無いのだが、裏ではこのような工作が行われていることを知れて、考え深い内容でした。
ネタバレを読む

原発ホワイトアウト
若杉 冽
本棚登録:0人
雑学の本 いつか、本当か?っていう疑わしいネタもあったが、まあまあ面白かった

話してウケる! 不思議がわかる! 理系のネタ全書
話題の達人倶楽部
本棚登録:0人
土地活用の本 どんな土地にどんなものを建てたら良いのか、古い建物をどうしたら投資利回りを上げれるかなとが書かれているが、どれも土地条件が限定的で再現性がない内容だった。あまり役に立たない。読む時間も三十分程度で十分
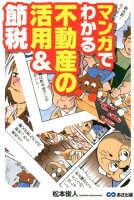
マンガでわかる不動産の活用&節税
松本俊人
本棚登録:0人
将来可能性があるのかなと思い、不動産投資の本を購入。株より中がブラックボックスといわれる不動産業界での投資であるため、どんな不正が跋扈しているのか、からくりがあるのかを知るために購入。 具体的には融資申請時の書類改竄(年収や貯蓄額を上乗せ。主にスルガ銀行向け、大手銀行は改ざんがバレると取引停止となるため対象外)や表面利回りの罠、家賃保証の罠などがある。不動産屋さんは人当たりが良いため騙されやすい。 世間知らずかつ高収入の医者や、一流エリート(自分に自信があり、ローンも組めるためリスクに盲目になった?)がカモにされているようだ。ただ低所得者や高額債務者も手出し不要と諭され、不動産投資の闇に足を突っ込んでしまうようだ。 業界人にコネがあるなど、最低限精通していないと厳しそう。投資はタイミングがすべて。買うのを迫られるような上昇市況では手を出さない方が吉
ネタバレを読む

新書718 やってはいけない不動産投資
藤田知也
本棚登録:0人
下町ロケットのモデルとなった植松電機の社長である。植松努さんの話である。 本の内容は、小中学生でもわかるような簡単な日本語で書かれている。 個人的な大事なポイントは、 ・どうせ無理と思わないこと ・好きなことをいくつもやって良い ・人がいやなことの理由を考えること 好きなことをいくつもやっていいというのは,心が軽くなった。仕事でまだまだできないことばかりだけど、deep learningについても興味があるから、それらしい仕事に着手しても良いんだなと思えた。
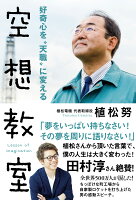
好奇心を“天職”に変える 空想教室
植松 努
本棚登録:0人
人口知能は、人間を理解することで発展できる。一方で、どこまで人間らしさを持たせるかは議論が必要である。 AIが進むことで、誰が責任を負うのかが曖昧になる点を解消できれば、日常生活にもっと組み込まれていくだろう。 学びは、AIにも寿命が必要で、新陳代謝させた方が、変化に対応したAIが作れるということである。

東大准教授に教わる「人工知能って、そんなことまでできるんですか?」
塩野誠/松尾豊
本棚登録:0人
ニュースに関する質問を使い、私を交えた知識を用いて筆者が回答する形式で物語が進んでいく。2016年と今から7年前の本ではあるけれども、世界史は不変なので、この本を手に取った印象深かったのは、ユダヤの話と中国の存在である。 まずユダヤのついての話であるが、世界への戦争や紛争は根本に宗教がある。イスラム教とキリスト教は、ユダヤ教から派生した宗教である。ユダヤ教は、厳し過ぎる、立法を持つイスラム教は、比較的ユダヤ教と類似している。一方で、キリスト教は厳しすぎる律法を、否定したため、一般人にも受け入れられることで大きく布教した宗教である。もともとユダヤ教を元とした2つの宗教は、いわば、親戚のような関係で、一度対立すると憎悪が生まれ、なかなか和解できない。 また、中国についてであるが、中国は共産主義で報道関係やデータの取り扱いは国家が行って、第三者からのチェックがないため、対外的に報道している内容は信憑性がない。また、当時、沖縄の米軍基地問題が取り上げられていたが、もし沖縄から米軍が撤退したとしても、中国の分が攻め寄ってきて、沖縄に岸が作られる可能性も否定できない。中国は同じ手法で、東南アジアの国に基地を作った。つまり、沖縄から米軍基地が撤退する事は、沖縄の独立につながるかもしれないが、将来を考えると、沖縄を不幸の未来に導くかもしれない。
ネタバレを読む
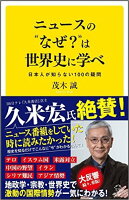
ニュースの“なぜ?”は世界史に学べ
茂木誠
本棚登録:0人
話が通じない人の特徴 それは物事を絶対と決めつけ、多面的に捉えることができない人。 一度一元的に捉えると、なかなか多次元的には戻れない。ただ一元的な人は、芯が通ってるとの見方もできる。これが正しいような世の中だが、果たしてそうなのか、疑問が残ることを指摘している。 僕的には、人としての根っこの部分には一元的(普遍的)にとらえ、枝葉の部分は多面的にできたら理想と考える。
ネタバレを読む

バカの壁
養老孟司
本棚登録:123人
ドラッカーのマネジメントを小説ベースで分かりやすく説明されている。 組織は顧客が誰かを明確にすることが必須である。 サラリーマンである以上、経営を実行するのはキャリアを積んだ先にある。しかし一般社員でも高い視座で業務に取り組むためには、知識として身につけておいて損はないと思う。 適材適所に人材を使うこと、結果にコミットすること、適正な評価を行うことが経営には必須である
ネタバレを読む

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら
岩崎夏海
本棚登録:0人
エネルギー地政学について、資源国・輸入国•発展途上国の絡み合い、更には現在進行中のロシアウクライナ問題を絡めて、まとめられていた。 主要の石油資源産油国は、アメリカ•ロシア•中東である。アメリカは一度石油資源が枯渇し、世界での立場が危うくなりかけたが、2000年代後半のシェール革命で、その地位を奪還した。ロシアは、国際エネルギー市場で重要なポジションをもうアメリカをはじめ、多くの反ロシア国から経済制裁を受けている。しかし欧州は地理的に近いこともあり、ロシアから多くの石油資源を輸入しているため、対ロシアの経済制裁が容易でなく、複雑な問題を抱えている。日本は、これまでロシアとはフリーアンモニアや水素のサプライチェーンの構築を目指していたが、戦争の影響で難しくなるだろう。 続いて、主要な資源消費国は、中国•アメリカ•インド•ロシア•日本である。近年中国が日本のLNGの保有量を抜き、世界一位に台頭してきたように、中国のエネルギー消費の追い上げが凄まじい。インドも人口ブーストで、エネルギー消費が増加している。どちらの国も,先進国の2050年カーボンニュートラル目標から10年遅れた2060年に目標を立てている。 日本はエネルギー市場において、板挟み的な位置にいる。これによって、動き方が難しくなっているが、産油国-アメリカ間に立ち、潤滑油のような役割が期待される
ネタバレを読む

エネルギーの地政学
小山堅
本棚登録:0人