匿名ユーザー
レビュー
やっと最後まで読めた。 初めの頃はアニメだし、途中は殆ど読めて無い。でもマインとフェルディナンドの幸せを確認出来たから良しとする。それにしても、ラノベがこんなに勉強になるとは思わなかった。グーテンベルグ、プランタン商会、アレキサンドリアなど歴史的に本や図書館に関するワード満載で、作者の本に対する思い入れや造詣の深さが良くわかる作品だと思う。 こんなにのめり込める作品を読めて感動したし、本好きに出会わせてくれたAmazonにも感謝かな?でも図書館がこの作品をあまり重視していないのがちょっと不満。日本だってここまで本が普及して、活字が溢れた社会になってまだ100年も経っていない。確かに識字率に関しては世界有数の国ではあるし、それは歴史的に見ても確かだろう。けれど今回オランダを勉強して、オランダの歴史を知って「井の中の蛙大海を知らず」という諺を実感した。海洋国家オランダは中世から情報の重要性を知っていた、印刷、出版、新聞等の分野の発展がどこよりも早い。ヨーロッパの中規模かやや小規模な国家の為に、途中で大英帝国に取って代わられたが、それにしても先駆けて情報分野の発展を牽引した国へのリスペクトを感じる。イギリスやフランス、ドイツ(プロシャ)などの大国を周囲に控え絶え間ない戦争に見舞われ、さらに国内でも宗教紛争に明け暮れながら、自分達の望む国家を建国した事を知って本当に尊敬する。オランダを調べていても中々本質を読み取れずに、苦労していたのが、本好きを読んで感覚的にわかったように思う。国が成長するという事はそこに住む人も成長するということ。又、成長する為の土壌やタイミングが重なる歴史の必然を感じる。日本の幕末、明治を勉強してもそこで自分の与えられた(もしくは自分から望んで)役割を完遂する為に命懸けで努力した人々を沢山知った。これはただ歴史の真実を知る為の本からは中々読み解く事が難しい。物語を読む事で、その時の人々の心情や流れを想像できて初めて腑に落ちたのだと思う。とにかくこのタイミングでこの本を読めて良かった。

本好きの下剋上第五部「女神の化身Ⅻ」(5-12)
香月美夜
本棚登録:0人
蔦屋重三郎の生涯を仕事(貸本屋と本屋それと出版)から追った本📕 吉原に生まれ育った蔦屋重三郎は、最初は吉原を足掛かりにした小さな貸本屋から始まった。出版の仕事に関わるのは、鱗形屋の出す吉原細見の改の件から…そして耕書堂(蔦重の店・吉原の近くにあった)として細見を出すようになる。 細見とは…吉原細見はそれを売って利益を出すようなものではなく、廓屋からお金を出してもらって、そこの遊女の宣伝広告の為に出す草子である。出来上がった細見は遊女がお得意様に配ったりするのが主だったようだ。柳澤米翁の宴遊日記にも細見の記事 がある。 初期の頃は他には富本節の稽古本や寺子屋などが 使う教本 庭訓往来等の利益は薄くても長期に渡り 売れる確実な出版物を手がける事で経営基盤を整え た。これは安永中期蔦重二十代の頃でそこから天 明期にかけてブームが起こった狂歌や戯作の絵双子 の出版と関わり狂歌界と持ちつ持たれつの関係性を 築きつつ蔦重という己のブランドを売り出して行く。蔦重と狂歌界との蜜月は天明期でほぼ終わる。 時代は寛成に移り出版統制は所謂寛成の改革で厳 しくなって行く。タッグを組んだ狂歌界も出版という機能が付与された事で熱狂が醒めてしまう。 そして寛政の改革はついに犠牲者を出してしまう。 武士でありながら絵草紙の作者として活躍した恋 川春町は自殺してしまう。朋誠堂喜三二は江戸留守居役を解かれ国許に都落ちする。山東京伝も手鎖の 罰を受ける。蔦重は資産を半分没収された。 しかし、蔦重はそこからも凄かった。問屋仲間の株 買い絵草紙よりも手堅い書物・本の取り扱いを始 めた。寛政の改革により起こった人々の自学ブームに乗ってその頃起きていた国学のブーム本居宣長に 名古屋まで会いに行き名古屋の新興書物問屋とタッグを組んだのだ。この辺は大田南畝の紹介なども あったかもしれん。 逆境にあっても乗り越えるしたたかな商売人の蔦重 も病気には勝てなかった。脚気とも結核とも言われたらしい病により寛政9年に生涯を閉じた。宝暦元 年に生まれた蔦重は47歳という若さで亡くなった。 当時のエンタメの総合プロデュースを成し遂げた蔦 重初代の凄さは養子を取って重ねた3代まで数えるも その仕事は継ぐ事は叶わなかったようだ。因みに、 3代目は名古屋の永楽屋の弟という話があるそうだ。 晩年に縁を結んだ名古屋の書物問屋の線は有りとも 書かれていた。 出版禁止や焚書されても蔦重初代の仕事は私達の目にも残された。彼が育てたとも言える歌麿や馬琴、 彼は確かに後世に誇れる物を残したのだ。かなり 難解な文章で読みにくい作品名だが、作品を通して 蔦重の生涯を見事に紹介してくれていると思う。

蔦屋重三郎(1067;1067)
鈴木 俊幸
本棚登録:0人
この本で指摘しているように医療は行き過ぎると確かに私達のシステムを破壊するのだろう。日本は世界に誇れる健康保険制度を持つが故に、コストを度外視出来る素地がある。そしてその事に寄って誰も(著者以外)コストの問題について言って来なかった。しかし、今のままの野放しの状態ではある日突然崩壊してもおかしくないところまで来ている事が良くわかった。人の命に値段はつけられないのは自明の理ではあるが、全体を考えた時にはやはり何処かで線引きする必要がある事を実感した。現状を良しとしていては次世代が割を食ってしまう。そうならない為に矢面に立って批判している筆者に尊敬の念を覚える。そして、この問題は渡辺淳一も違う角度で作家になった当初に指摘していた。医療の発達に伴って本来であれば助からなかった命が助かる。それでその後普通に生活出来る迄に回復すれば良いが、重度の後遺症が残る場合が多々ある。家族は最初は命が助かって喜んでも、その後全てを犠牲にしてその面倒を見る立場になる。野田聖子議員の子供にしても彼女のエゴで産まれた子供が本当に幸福なのかと考えると、それは手放しでは認めにくい。こういった問題は議論そのものがしにくい事もあって、問題から目を背けがちだが今後の事を考えるとやはりきちんと議論しなければいけないように思う。しかし、私の嫌いな瀬戸内寂聴に言及していたのは笑えた。筆者の言う通りだと思う。彼女のように自分の生きたいように生きて周りを振り回した人間が、しかも仏門に入って煩悩を落としたはずなのに関わらず、生に執着するとか…何のための信仰?仏門に入らなくても自分の生を全うして慫慂として召される方も多いと言うのに。まぁ、最後まで悪あがきするのも又彼女らしい人生なのかもだが、とにかく彼女は反面教師としては最高の人だった事は確かだろう。笑笑

医学の勝利が国家を滅ぼす
里見 清一
本棚登録:0人
最近徳川慶喜家のお墓の墓じまいが話題になったが、そのお墓を任された山岸美喜さんが祖母の残した手記を出版した物。 この祖母は名を徳川和子という。そして旧姓は松平で会津藩主の家に産まれた人だった。会津12代藩主松平保夫(もりお)を父に沼津藩主4女の進子(ゆきこ)を母にする。高松宮妃喜久子様は和子の従姉妹にあたられる。大正6年に産まれて平成15年(2003)に85歳で亡くなられた。彼女の夫は徳川慶光(戦前迄は公爵)であり、その後は息子の慶朝という方が継がれたのだがそこで絶家となったのだ。叔父である慶朝との交流を続け最後まで世話を続けた筆者の山岸美喜さんがお墓と松戸市の戸城博物館に預けられた膨大な遺品(徳川慶喜家の史料)を託されたのだ。『みみずのたわごと』には大量の写真も掲載されており、華族の生活を伺えると共に時代の変遷も追えるとても貴重な史料だと思う。何気に手に取ってみたが、面白かった。

みみずのたわごと
徳川和子/山岸美喜
本棚登録:0人
いわゆる明治維新を経て徳川幕府を倒した薩長が、関ヶ原の怨念を晴らして政権を握った。そして、私達はそこから薩長が紡ぐ歴史感の中で歩まされている。今までずっと幕末を調べる事があっても会津の事は敬遠してしまっていた。それはそこで何があったのか?どういう事が行われたのか?何となく想像が出来るからこそ読んだり聞いたりすることから逃げていた。 しかしこの本を読んでやはりあまりにも知らない事が多すぎると感じたし、未だに明治維新に関してここまでの怒りを覚える人がいる事にも軽く衝撃を受けた。勝者の紡ぐ歴史を鵜呑みにするつもりは無く、幕末関連本を読むとイライラする事も多かったが、私が感じていた長州人は間違っていなかったのだとも思えた。吉田松陰が礼賛されるのが私には全然わからなかったから。伊藤博文、井上馨、山縣有朋に至ってはこんなチンピラや犯罪者に日本の近代の舵取りをやられたのが物凄く納得が行っていなかった。そこをバッサリと断罪しているのは爽快だった。人は人、自分は自分で何を感じるかは個人の自由とはいえ、あまりに人と違うとやはり不安になる。それがこうも見事にこき下ろしてくれる人がいて本当に嬉しい。 幕末の尊皇攘夷も意味が分からない所が多かった。私が知る限り幕臣の方が勤皇の本当の所を知って体現している人が大部分だったから、それこそ薩長は知れば知るほど尊皇攘夷って何か知ってるの?って人が多い。この皮肉!!だから読めば読むほどわけらないというか矛盾に突き当たる。幕末関連で傑物とか維新の精神的支柱なんて言われた人ほど、全然そうは思えなかったから、それがこの本を読んでスッキリした。読めて良かった。

明治維新という過ち改訂増補版
原田伊織
本棚登録:0人
宗教戦争が悲惨な理由…宗教が理由でやめられなくなるから 「何故神の声を聞くのにバチカンを通さねばならないのか?」神学者ヤン,フス 英仏100年戦争でフランスに勝利をもたらしたジャンヌ・ダルクは「神の声が聞こえた」ということでバチカンに殺された。フランスのシャルル王太子も恩人のジャンヌ・ダルクを見捨てた! 史上最強のローマ教皇 1198年就任のインノケンティウス三世 「全宇宙の創世主である神は、天の大空に二つの大きな発光体を置いた。大きな光に昼を支配させ、小さな光に夜を支配させた。これと同じように、天と呼ばれる普遍的な教会の大空にも、神は二つの大きな栄誉ある職位を制定した。大きい方の位には昼にたとえられる魂をつかさどらせ、ちいさい方に夜にたとえられる肉体をつかさどらせた。この二つの位とは教皇の権威と王の権力である。月はその光を太陽から受け、事実、量においても質においても、地位も効力も太陽におとるものである。それと同じように王はその権力を教皇の権威から受け、教皇の権威に近づけば近づくほど、王の権力の光は薄れ、遠ざかれば遠ざかるほどその光は増すのである。」 就任時の挨拶 16世紀のキリスト教 「異端の罪は異教の罪より重い」宗教戦争は相手を皆殺しにするまで終わらない…怖すぎる😱

並べて学べば面白すぎる 世界史と日本史
倉山満
本棚登録:0人
円の誕生に纏わる謎を追った本。 とはいえ、これは史家や専門家の間では、明治初期の皇居の火災によって公文書が消失した事に寄り、公文書での確定が不可能とされている事になっている。 円の前史とも言える1800年代初めからの、幕末の私文書を通して、幕末の知識人の間では円はちょっとした流行り(というか先端)として、幕府への反発心からなのか、例えば高野長英や橋本左内などの私信に使用されている。又、明治初期のまだ江戸時代の貨幣が流通している時にお寺への寄進を記録したパンフレット様の物にも円が記載されている事例があって、前史も70年近くにも及ぶと知識人だけではなく、一般の人々にもそれなりに浸透していたのではないかとの事例もあげてあった。 このように、円の名称の誕生のはっきりとした公文書自体は発見されずとも、この議論のかなり以前から円は日本人の間で通貨の名称として普及し始めていたのではないか。ようするに明治2年3月4日の参与会議で形状と十進法の採用などの決定を見たが、名称までの議論はなされなかった。その後外交文書に登場した物(明治2年7月2日)の確認が取れただけどなっている。 そして明治4年の新貨条例の公布で突然「円」が登場したように見えるのである。 この辺を丹念に幕末の文書を追うことで、円の誕生を位置づけした本だと思う。

¥の歴史学
三上隆三
本棚登録:0人
慶応4年から明治4年、大隈重信の29歳から33歳の時をピックアップして、幕末維新時の日本の弊制改革を取り上げた小説。 江戸時代の弊制からの脱却を図り、新しい国日本の通貨を誕生させる為に苦心した大隈重信(大蔵省の実質的なトップ)の物語である。御一新との事で形状から単位、更に名称までの全てを新しい物にと思考する過程のドラマも面白いと思った。が、この新しい弊制改革は日本一国の物ではなく、貿易や外交を通じての諸外国との関わりをも巻き込んで、日本の幕開けの1つであった事が良くわかった。 薩摩と長州の藩閥をバックにする政府の他のメンバーとの確執と戦いながら、自分だけの実力で大蔵省のトップに立って諸外国との交渉にも挑み続けた大隈重信…彼の幼少期からの教育や彼を育んだ佐賀藩をやはりもっと知りたいと思った。墓は護国寺にある。

小説・大隈重信 円を創った男
渡辺 房男
本棚登録:0人
紀伊國屋文左衛門 年表、家系図あり 結構面白い

紀伊国屋文左衛門の生涯
山木育
本棚登録:0人
まぁまぁ面白かった。 作者が新潟出身で二松学舎大学というのもなんか親近感🤣 シリーズ化すれば良いのに、後の展開が出てこないのか?女性だけの探偵社の設定も良かったのに… ラノベだからか?そこまでの仕込みを出来ないのか?でも人間関係もキャラ設定も性格などを考えると関係性を発展させられれば面白そうに思えるのに残念!恋愛要素が無いと受けが悪いのか? 若い子よりも少々年が行った世代の方が受けるのだろうか? 「薬屋のひとりごと」はまだアニメだけしか観ていないから、小説を読まないとなんとも評価は出来ないが、山田悠介の小説のような嫌な後味も無いし、良いと思えるのだけど、うーん🤔
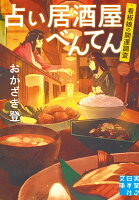
占い居酒屋べんてん
おかざき登
本棚登録:0人
中尾光莉(子持ちのコンビニパートでWeb小説家) 志波三彦コンビニ店長 フェロモンお化け 廣瀬太郎 コンビニバイト大学生 志波二彦 三彦の兄何でも屋 采原或る ラノベ好きのアイドル光莉の推し Quickのメンバー内では目だだない 志波樹恵琉 志波兄弟の末っ子 神崎華 華の姉が二彦の元カノの翠 華が人生をかけた夢が叶おうとした時に、翠に骨髄移植が必要になり夢を断念…(その時に二彦に代償としてセックスを要求する。華は元々二彦が好きだった)華と翠の姉妹は親に差別されて育てられた。二彦と翠は華との事を知った翠の狂乱で別れた。二彦は翠が助かる事だけを望んだが、後に華が夢を断念した事、姉妹差別の事等を考えて、華のあまりに辛い人生を思い、二彦自身は華に禍根は残していない。今回の第3話で翠の結婚を知らせ、翠が幸せになっている事を知り、更に華への好感が増す展開。 そして、翠の結婚式に連れ出された太郎は華に恋をする。 今度の3は店長よりも周りのキャラ達が、活躍する。采原或るも光莉の推しというだけではなく、自分から積極的に光莉達のコンビニに関わって来て、テンダネスを取り巻く人々が更に面白くなって来た。 作者は三彦を書くのに疲れたのかな?其れよりも周りの濃いキャラ達に引っ張られて、そちらを書く方が楽しいのかも…ともあれ、今回も面白かった😂
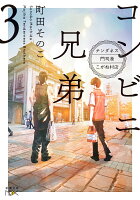
コンビニ兄弟3
町田そのこ
本棚登録:96人
読んで良かった。 歴史学者として災害史を書いていて、私が知りたかった事が結構書かれていた。 災害史に取り組まれたのが、家族の津波体験ということで、身内の実体験を書いてあったのも、とても教えられる内容だった。災害にあった時に自分の事は自分で守る気持ちが一番大切だという事も伝わってきた。避難も避難した後も自助努力無しでは、周りに迷惑がかかるばかりでなんにもならないのだと知れたのは大きい。 本郷さんも書いていたが、最近は文系理系の垣根を越えて、学会(?)が開催されて、災害の事も共同で研究する土台が出来ているのも良いと思った。古文書を読むのはやはり歴史学者が得てだろうと思うし、読んでもらった文章から科学的な検証を地震学者などが行えば、歴史上の災害の規模などの研究も進み、将来起こりうる災害へのシュミレーションの推測も、東日本大震災の時に良く言われた想定外という言葉を聞かずに済むのかとも思う。 同時に同じ災害にあっていたとして、自治体に寄っては過去の教訓を活かし、被害を最小限に抑える事が出来たなど、やはり自治体ごとのバラツキが起きるのも国の施策がキチンとしていないのだと思わざるを得ない。その自治体の首長の取り組み次第で変わるのは、同じ国に生活していて、釈然としない。政治家は本当に何を考えているのだろう?何も考えていないのかもしれない。数だけいても誰かがやればいいという事になりかねないから、もっと少数精鋭にするべきだと思う。

天災から日本史を読みなおす
磯田道史
本棚登録:0人
2023年、関東大震災から100年の節目の年に出版された本。本所の被服廠跡での生々しい被災体験から、40年後に起きた新潟地震の時に、回想した文章などが載せられている。同じ災害を経験したけれど、実際に居た場所に寄って個々人でその体験は全く違う。だからこそ、記録に残る数字や写真だけでは知りえない震災時の体験が感じ取れる。普段から文章を書く仕事をしているからか、行動や感情の動きなどが書かれているので、追体験している気分にさせてくれる物もある。 又、作家だけではなくホテル支配人や政治家などは、その職業に沿った震災に対する備えなども書いていて、教訓になる。

関東大震災 文豪たちの証言
石井正己
本棚登録:0人
埼玉県熊谷市の見性院というお寺の現役の僧侶の書いた本。奇しくも曹洞宗だった。 私がずっと感じていた疑問への回答をくれる内容だった。実際に出来るのかはともかくとして、著者も言うように信仰は家単位では無く個人の物だと思っていた。特に結婚した婚家の宗教が創価なんて、なんの間違いかとずっと思っていた。別に日蓮宗でも構わなかったが、創価は別。又、学会葬も私は無理だと思った。不受不施派の頑なな考え方も受け付けない。確固とした宗教観がある訳ではないが、あの排他的な考え方は、表立って反論出来ないから尚更嫌悪感さえ抱いてしまう。学会の幹部の倫理観も眉唾で偽善としか思えない。実際、集まって経験談を語り合うようだが、本当に私には入れない世界。 おばあちゃんの事は好きじゃないけど、あの真っ直ぐな信仰心は尊敬するレベルだから、尚更学会幹部のやり方が気に食わない。末端の信者の素直な信仰心を弄ばないで欲しいと強く思う。創価のせいでどうも日蓮宗に対してもあまり良く思えない。お墓はパパと一緒で良いけど、送って貰うのは出来れば自分の選んだ僧侶に送って貰いたい。パパが忙しすぎて、そういう話が全然出来ないが、菩提寺を持つのか、お墓をどうするのか?色々考えてしまう。見性院さんがもっと近かったら、予約してしまいたいくらいだ。やはり、僧侶と言えど宗教家なのだから、もっと普段から私達の近くに居るべきだと思う。そういう意味ではまだ神社の方が一般人の近くに居るのではと思う。お寺も葬式や法事だけしていれば良い時代じゃないのは確かだと思う。

お坊さんが明かすあなたの町からお寺が消える理由
橋本英樹
本棚登録:0人
2013年9月に書いたブログを元に筆者が、関東大震災について書いた本。丹念に現場を周り証言を集めている。災害が起きたまさにその時に、一体何が起きたのか?どうして流言蜚語が生まれそれが拡散されて行ったのか?をこの丹念な取材に寄って疑問から回答に近い物を提示してくれていると思う。そしてこの本には、現在(2013)が書かれている。新大久保で始められたヘイトスピーチに現在でも決して無くなっていない、韓国人に対する差別は、未だに日本人が震災の頃と変わらぬ問題を抱えていることを突きつけている。きちんと関東大震災の時の朝鮮人大虐殺を認めて、その責任に向き合って来なかったツケなのかと思う。いくら民間人が善意で調べて慰霊碑を建てたり、本を出して啓発活動を行う事で風化を防ぐ努力をしても、この本にあるように姿を変えて何処かに差別が吹き出してしまう。人の心は複雑だからどんな人間にも闇の部分はあると思う。それが非常時に自分でも知らない内に負の感情に飲み込まれてしまうのではないか?特に関東大震災前の日韓の情勢では下敷きがこれでもかと言うくらいにあった訳だ。でも現在でもそれは変わってないのでは無いのか?嫌韓が叫ばれて、一時は書店に嫌韓本が溢れていた。それは知らず知らずの内に人々の心の中に差別意識を育てて行くのだろう。恐ろしい事だと思う。『ねじ曲げられた桜』のように古代からの積み重ねられた記憶が作用して、次第に違う物が現われて悲劇を生み出してしまう。又、我々1人1人が知らない間にそれに荷担してしまう過程までを考えると、本当に恐ろしい事だと思う。報道されない、報道出来ないような現実がある事を忘れてはいけないと思った。

九月、東京の路上で
加藤 直樹
本棚登録:0人
下巻は最初の方は涙が出て中々読み進めるのが辛かった。又、全巻を通じてあまりにも難しくて正直全然理解が及ばなかった。けれど、9.11の自爆テロと第二次世界大戦末期に日本兵による特攻を同一視する事に対しての彼女なりの回答なのだとは思った。特攻隊に志願した学徒兵の多くが、決して本当の意味で自ら特攻を望んだわけではないのもわかったし、ましてや天皇の為などでは無いことも!(まぁこれは読む前からわかってはいたが)日本の歴史の中で何故桜が特攻や戦争で散った兵士達を象徴する物になったのかという複雑な過程を詳述する為に、ここまで難解になってしまったのか?でももう少し一般人が読みやすくしてくれないと、せっかくの彼女の思いが多くの人に届かないと思う。それとコミュニケーションについては、確かにそうだと思えた箇所あった。コミュニケーションに限らず同じ景色を見ても人によって見ている物も感想も全く違ったりするし、同じ言語(日本語)を話していても会話の通じない人はいる。私がこの本で残念に思ったのは、過去に起きた誤ちが何故起きたのかを解き明かしてくれたなら、もっと読みやすい方が今後の教訓というか、参考になったかもと思ったからだ。でもここまで複雑な過程を経た文化の衣を纏った見えにくいイデオロギーに誤魔化されたなら、それを回避するのは難しすぎる。ネット社会になって誰でも発信する事が可能になってしまった現在では情報の取捨選択だけでも本当に大変😰ウクライナとロシアの戦争が始まって、去年はイスラエルまで戦闘を始めるし、元々ウクライナ戦の自体で第三次世界大戦は始まっているという見方もあるようだし、世界規模で未来がどうなるのか益々混沌として来てしまった。戦争が無くても日本は常に災害と戦っているような国なのに(元旦には能登地震もあったのに)本当に憲法から9条は無くしてはいけないと思う。『人間が歴史を作る』などは違うというのは良くわかった。法律1つにしても最初に意図したように運用されない事だって多いし、ある程度は読めたとしてもそれは短期間であって、時代が下る内になんでも変質してしまう。例えば忠臣蔵だって、多分1人1人であの行動にかけた思いは違ったはずだし、後世芝居になった時点でもう全く別物だっただろう。私達が出来るのはせいぜい書き残された物を検証する事だが、書き残されなかった思いは永遠にわからない。やはり歴史に意味は無く、事実がそこに有るだけだろう。 「隊員達は死ねば自分の魂が靖国神社に祀られることを承知していたが、神となるために死ぬことを選択した訳では無い。」海軍航空学試験研究所の技術士内藤 「彼ら(特攻隊の生き残り)は、自分達が命を犠牲にすれば何かが変わると純真な気持ちで信じていた若い頃を懐かしんで靖国に集まるのである」「彼ら(生き残り)は、死んだ仲間達の最期の言葉が「靖国神社で待っている」であったから靖国に集まるのである」

ねじ曲げられた桜(下)
大貫 恵美子
本棚登録:0人
小山田与清(おやまだともきよ)を中心に江戸時代の蔵書家達について書かれた物。特に塙保己一の部分は気になる。江戸時代にこういう市井を含む好事家達が自分の蔵書を含めて、貴重な文献を遺してくれたのが知れた。最近気になっている本郷和人さんの史料編纂所の仕事は塙保己一の仕事の継承だと思うと感慨深い。平安時代から連綿と続いた学問が次第に成熟して、江戸時代についに国学を体系化したのかとも思う。平田篤胤は知っていたが、小山田与清はこの本で始めて知った。平田篤胤の思想はよく分からないが、与清の仕事は現代の私達にも貢献してくれていると感じる。書籍目録しかり、索引しかり…与清が扱った書籍は直接自分が読むことは無くても、彼がやった仕事は確実に本を選ぶとか、図書館のシステムにも反映されていると思う。 又、書籍に関する彼等の情熱は羨ましいくらいにわかる。そして蔵書家達のネットワークにも羨望を感じる。自分にも好きな本を語る仲間が欲しい。盲目の塙保己一の仕事には疑問しかなかったが、この本を読んで小山田与清や大田南畝らの仲間達も一緒に仕事をした事もわかったし、今現在本を読んでいて、読み方が分からなくて勝手に漢字の意味でスルーしてしまうけど、塙保己一の場合は音が絶対に必要だった訳だし、校閲の事を考えると尚更厳密に出来たのだろうと思った。しかし塙保己一の頭にはどれほどの書籍が記憶されたのだろう。彼の場合はその記憶は何時でもアウトプットが可能な物だったと考えると不思議な領域にも思える。日本でも古来には稗田阿礼という記紀を記憶する専門家がいた事を考えると、稀にそういう能力を持った人はいるのかと思った。ただし、文字が記憶の役目を担う事になって、人間はその能力を失ったのではと思う。便利になるという事は、何かを失う事にもなるのかもしれない。

江戸の蔵書家たち
岡村 敬二
本棚登録:0人
つい最近山本博文さんが亡くなっていた事を知った。ショックだった。専門が近世史なので著書を読む機会が多い先生だった。わかりやすい文章で江戸を解説する本が多かっただけに残念でならない。本書もその1冊。有名な赤穂浪士をフィクションから離れた実態として捉え直す物。それと赤穂事件に関してその善悪の判断が大きく別れる所だが、元禄時代迄の当時の武士の心理に沿って、解説を試みていて余計に好感が持てた。江戸時代の武士と現代に生きる私達では倫理観から何から全く違う訳だから、彼らの行動を愚挙だとこき下ろすのは絶対に違うと思った。それと吉良の養子の左兵衛が1番の被害者ではとも書いていて、そこにも好感が持てる。

これが本当の「忠臣蔵」
山本 博文
本棚登録:0人
東京大学資料編纂所の教授・本郷和人氏の著書である。文章自体もくだけているし、内容も素人にもわかるように平易になっていて読みやすい。生まれ年が同じな所から手に取るようになって、最近になって歴史に興味を持ち出したけれど、なんだか親近感が湧いてくる。感じ方が似ている気がするのと、勉強していて感じる疑問に答えをもらっている気がする。中島敦にハマった下りも益々似ていると思った。でも読んでいるだけで本当に膨大な量の本を読んだのが伝わってきて、それだけでも尊敬出来る。奥さんと同じ職場で彼女の方が上司との事だが、どちらも仕事がしにくいとかいう事は無いのかと思った。妻を若い頃からリスペクトしているのが、自然に伝わってくるのも好印象である。

歴史学者という病
本郷和人
本棚登録:0人
