レモネード
レビュー
読みやすいし面白い。内容は大人向き。作中の主人公の父の「人生というのは川みたいなものだから、何をやってようと流されていく、安定とか不安定なんて、大きな川の流れの中では些細なこと、向かっていく方向に大差がないなら好きにすればいい。」という言葉が印象的。随所に出てくる実話の小話が教養を深めてくれる。例えば、ゴッホがレンブラントの「ユダヤの花嫁」を観たときに、「もう二週間この絵の前に座っていられるなら、十年寿命が短くなってもいい」といったなど。
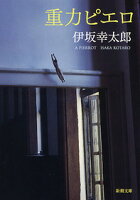
重力ピエロ
伊坂幸太郎
本棚登録:476人
まずまず。切ないラブストーリー。ちょいちょい出てくる作者の表現があまり好きではないので飛ばし読みした。
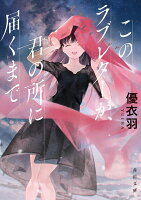
このラブレターが、君の所に届くまで
優衣羽
本棚登録:0人
私も同じように「登るならエベレストではなくK2」と言っていた。作者の思想に共感が持てる。

エベレストには登らない
角幡 唯介
本棚登録:0人
全3巻。 1⃣ 神の山 マチャプチャレ 2⃣ 真実の山 アンナプルナ 3⃣ 魔の山 ナンガ・パルバット 原作は「K」と同じであるため、複雑な過去を持つ日本人登山家が活躍するところはかなり似ている。 クライミングシステムがありえなかったり、構成に無理があるため、悪評もあるが、マンガだし、私は特に気にならずに楽しめた。 内容自体は、かなり面白く、続きが是非読んでみたい作品。 ナンガ・パルバット編では、アフガニスタンへのアメリカの武力介入が題材となっており、2019年にアフガニスタンで亡くなった故・中村哲医師のことを思い出した。 正義とは何か、考えてみる。

しずかの山(1)
松本剛/愛英史
本棚登録:0人
全5巻。 主人公の山岳カメラマン深町誠は、ネパール滞在時に「エヴェレスト初登頂の謎を解く可能性を秘めた古いカメラ」と遭遇する。 その後、毒蛇と呼ばれる謎の日本人男性、羽生丈二と出会う。 深町は、カメラの謎を解くため、謎を解く鍵を握る羽生の過去を探るが、知れば知るほど羽生自身に興味を持つようになる。 羽生はエヴェレスト南西壁冬季無酸素単独登頂を目指していた。 人類が挑める極限の挑戦、神の領域とも言える登攀を見届けるため、羽生に同行する深町。 そして…感動の結末を迎える。 本書はフィクションであるが、事実を織り交ぜながら書かれている。 羽生丈二のモデルは森田勝。ライバルとして登場する長谷常雄のモデルはもちろん、長谷川恒男。この2人のことをもっと知りたいと思った。 4巻後半からの羽生の挑戦と深町の挑戦、そして2人の想い。 胸が熱くなりっぱなしのクライマックス。 私もいつか、エヴェレストに登ろう…
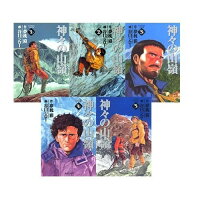
神々の山嶺文庫版コミック(全5巻完結セット)
夢枕獏/谷口ジロー
本棚登録:0人
スーパー爺さんの挑戦記。 三浦雄一郎氏は、若い頃にスキーで速さを競う競技で、時速172kmという当時の世界新記録を樹立したというとんでもないクレイジーなお方。 その後も7大陸最高峰からの滑降に成功するなど挑戦を続けていたが、還暦を過ぎて挑戦から遠ざかっていた。 しかし、99歳でモンブラン氷河からの滑降に成功した父の三浦敬三氏(←バケモノ)や、オリンピックのモーグルに出場した次男の三浦豪太氏から刺激を受け、65歳のときに「70歳でエベレスト登頂を果たす」という目標を立て実現させる。 そして今回は75歳でのエベレスト挑戦記。 日記形式で記載されており、テンポよく進んでいく。 見事登頂し、「涙が出るほど、辛くて、厳しくて、嬉しい。」と語った。 三浦一家の挑戦を見ていたら、まだまだこれから何でもできる気がする。 人生今こそ出発点! 私も目標を定めて生きていこう。 それから、三浦氏は80歳で再びエベレストの頂上に立つことになる。 そして挑戦は続くよ…どこまでも。

冒険家
三浦雄一郎
本棚登録:0人
全1巻、短編8話で構成。1991年発行。 1⃣ 南西壁 2⃣ 裸足の壁 3⃣ 北壁 4⃣ 遠い頂 5⃣ ザイル 6⃣ ヒマラヤの虎 7⃣ 吹雪 8⃣ K2 山男やシェルパ族の勇者たちの生き様を描いた短編集。 どの話にも最後の方に盛り上がるシーンがあって胸が熱くなる。 南西壁の最後の笑顔、北壁の「時よ、止まれ!」のシーンが特にグッと来た。 また、K2の絶妙の終わり方もよい。

岳人列伝(1)
村上 もとか
本棚登録:0人
第1章 木曽駒ケ岳の学校集団登山事故(1913年) 第2章 剱澤小屋の雪崩事故(1930年) 第3章 冬の富士山巨大雪崩事故(1954年) 第4章 前穂東壁のナイロンザイル切断事故(1955年) 第5章 谷川岳の宙吊り事故(1960年) 第6章 愛知大学山岳部の大量遭難事故(1963年) 第7章 西穂独標の学校登山落雷事故(1967年) 第8章 立山の中高年初心者遭難事故(1989年) 第9章 吾妻連峰のスキーツアー遭難事故(1994年) 第10章 トムラウシ山のツアー登山遭難事故(2009年) 戦前から現在に至るまでの大きな山岳遭難事故について取り上げ、それぞれの事故が起きた原因を時代背景とともに考察し、どう対処すべきだったかについて記されている。 第10章トムラウシ山のツアー登山遭難事故は、記憶に新しいが、第1章木曽駒ケ岳の学校集団登山事故とまったく同じパターンをたどっている。 どちらも、夏に大人数を引率して登山中に悪天候に見舞われ、低体温症で行動できなくなるものが続出し、引率者はその対応に手一杯となって指導力を失い、パーティーは崩壊して参加者は散り散りばらばらに自力で下山する。 100年以上も前に起きた事故だが、トムラウシ山ツアーの引率者や参加者がこの事故の教訓を心に刻んでいたならば、また違った結果を生んでいたかもしれない。 歴史は繰り返される。歴史を学ぶことの重要性を改めて感じさせてくれた。 登山を趣味とする人は是非ご一読を。

十大事故から読み解く 山岳遭難の傷痕
本棚登録:0人
著者:植村直己 2008年新装版 主に五大陸最高峰に登るまでの軌跡について書かれており、これまで何度も読み返した私のバイブル(愛読書)。 大学で山岳部に入り、山に明け暮れた植村青年は、ガストン・レビュファ「星と嵐」を読んでアルプスに強い憧れを抱くようになる。 ヨーロッパ山行のため生活水準の高いアメリカでアルバイトしようと、英語もできないのに110ドルだけ持って移民船でアメリカへ向かう。 カリフォルニアの農場で労働許可証も持たずにメキシコからの不法入国者とともに3ヵ月程1日も休まずに働き、お金も溜まってきたころ移民局に見つかり、鉄格子の牢に入れられ日本へ強制送還されそうになるが、旅の目的を必死に伝えて、ヨーロッパ入りを果たす。 無知のまま、秋のモン・ブランの単独登攀に挑み、ヒドン・クレバスに落下。気を失ったが幸運にもクレバスの途中で引っかかって一命をとりとめる。 と前半からとてつもない冒険が赤裸々に書かれており、植村氏の情熱と純粋さがひしひしと伝わってくる。 その後も世界各地の山やアマゾンイカダ下り、そして冬期グランド・ジョラス北壁までの記録がテンポ良く書かれており、植村氏のとてつもないエネルギーには関心させられる。 著者あとがきにて 『私は五大陸の最高峰に登ったけれど、高い山に登ったからすごいとか、厳しい岩壁を登攀したからえらい、という考え方にはなれない。山登りを優劣でみてはいけないと思う。要は、どんな小さなハイキング的な山であっても、登る人自身が登り終えた後も深く心に残る登山がほんとうだと思う。』 心に残る登山か、、、ほとんど無いかも(-_-;)
ネタバレを読む
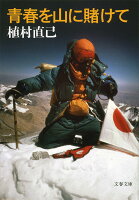
青春を山に賭けて
植村 直己
本棚登録:0人
全1巻、短編5話で構成。 ・K2 ・プモリ ・エベレスト ・マカルー ・カイラス カラコルム山脈の玄関、アスコーレ村でマウンテンポーターとして暮らす「K」。 国籍も名前も素性も誰も知らない。 そんな「K」が超人的な登山技術で山岳遭難者を救出していく物語。 獣に習った生き残る術で難局をクリアしていき、時には、突風に乗り、垂壁を逆立ちで登るなど、常識では考えられない技も見せてくれる。 元々4話「マカルー」までの作品だったものに、5話「カイラス」を付けているので、違和感があるが、どれも手に汗握る作品ばかりで読み応えあり。 是非ご一読を。
ネタバレを読む

K
谷口ジロー
本棚登録:0人
第1部 旅立ちの夏 第2部 白い風の冬 第3部 みどり甦る季節 1967年に厳冬期のデナリ(旧名マッキンリー)初登攀を達成した8人の若者?(22歳~39歳)の夢と挫折を描いたノンフィクション作品。 そのうちの1人が著者の西前氏である。 著者は、自分の代わりに児島次郎(またはジロー)という仮名で登場している。 零下50度、風速50m、高度6000m、酸素量は平地の半分、日照時間は7時間、無数のクレバス、荒れ狂うブリザードそして闇とオーロラ。 そんな、人類にとって未知の領域に現代とは比べ物にならないほどの装備で挑む。 西前氏はこの話をいつかは語りたいとは思いながらも、悲しみ、怒り等の複雑な感情の中で書き出すことができず、30年近い時を経て執筆に至る。 帰国後、高校教師であった西前氏は、「子ども劇場」の会員として高校生をアラスカへ一週間の冒険旅行に連れて行ったりとエネルギッシュに活動されていたようだ。 参加した高校生の作文が紹介されているが、かけがえのない体験を通して新しい自分を発見したというとても印象深い内容である。 西前氏談 「『いい体験をしたら、高校生は3日で変わる』と言ってね、その変わり目を待つのがつらいんだけど、きっかけさえあればみごとに変身するのを何度も見てきたよ。これが教師の醍醐味だよ。」 「『冬のデナリ』の失敗でぼくの青春、ぼくの冒険は終わったと思っていたけど、今、考えてみると人生の冒険は始まったばかりだった。日本の教師の仕事は教科を教えるだけじゃないからね。学校でも地域でも、現状から一歩二歩出ていかなければと力のはいることばかりで、その手ごたえを楽しんでいるうちに、気が付いたらもう退職の年なんだ。」 ふと、私の祖母が昔作った短歌を思い出した。 「ファミコンといふ化け物に取り憑かれし孫を連れだし七草を摘む」 私もパソコンばかりしておらずに息子たちを野山に連れだそう。

冬のデナリ
西前四郎
本棚登録:0人