
NIE
レビュー
楽しかった。 生業とする調理屋だからというのもあるが、人との触れ合いに臆することのない主人公に好感を持てる。料理だけでなく、人が好きなのだろう。 料理も見た目の描写以上に匂いを感じる部分も多く、読んでて味わっている気分になれる。私自身は軽いつわり中なので、もうちょっと落ち着いたときに読めばよかった。 旅に出て、その地を味わうことが風土や人柄を知る上でも大きいと思う。日本も小売業や流通の発達で画一的になっている側面が大きいとはいえ、やっぱり種々残っている。そういう食の奥深さや楽しみを思い出させてくれる一冊だった。 他シリーズも是非とも読んでみたい。

踊れぬ天使 佳代のキッチン
原宏一
本棚登録:40人
中々面白かった。関西弁でのセリフばかりだが、違和感もなくすっと読み込める。主人公が強い特徴を持ってないところも、平凡な女子大生として創造できて楽しい。特徴があるといえば、店長のバンダナぐらい? もう少し家具と関わり深い話の方が好みだけれど、過ぎると登場人物たちに特殊能力に近いような才能を持たせずには展開できないので、いい塩梅なのかもしれない。 日常の延長線上のような緩やかな舞台の中で、時折訪れる小さなミステリがスパイスのように効く。毎日食べられるカレーのような物語だった。

西洋古家具店アシュリと白い猫
岡篠名桜
本棚登録:0人
いい本だった。 被虐待児の半生といえばそうなのだが、ここにはその言葉から連想されるただただ辛く苦しい匂いはほとんどしない。どこまでも優しく、不器用な愛がこぼれ落ちていくようだった。その行為を善とはしない。主人公の母親は、愚かだし、どうしようもない人間ではあるのだ。ただ、そこから発した愛情までもが嘘偽りではないということを、主人公が抱き止める過程は、切なくも暖かな気持ちになる。それが一つの母子の決別にもなるのだろう。 作中、非常に短文だが、主人公に嫌な目線を向ける通行人が登場する。大した分量のない、ストーリーにも大きな影響を与えない箇所なのだが、妙に心に残った。彼らを失礼なやつだとか、心無い人間だと責めたり、憤慨することは容易だろう。ただ、現実、自分がその場に相対したとき、どんな行動ができるだろうか。彼らには彼らで理由があるのかもしれないし、自分自身は余裕のない時に心ある対応ができるのだろうか。 ロバの寓話も興味深かった。創作なのか、実際の寓話なのかは分からないが、振り返らないロバは、心の助けになりそうだ。その時のロバの気持ちは計り知れないが、同じような場面で、私もそのロバのようにありたい。

とわの庭
小川 糸
本棚登録:0人
数の不思議とファンタジーをかけ合わせてて、中々面白い。フィボナッチ数列とか名前しか知らなくて、実感として理解できたりするのが非常に面白かった。単なる数学で覚えた公式が、実生活に使えるような実学になっていくように思えて楽しかった。できれば、メモを用意して読むことをおすすめする。

数の女王
川添愛
本棚登録:0人
幻想的な言葉の羅列は、夢の中への招待状のようで、読者は非常に明確な言葉なのに、あやふやな事実の上を歩かされているように感じる。それがここちよいかどうかは好みだと思う。 思い出話と現在が入り混じり、そこに架空の話や見聞きしたものも区別されることなく、なんの分類もなく陳列されたショーケースのような手紙は、他者のプライベートな領域を人の手紙を盗み見る神になったような万能感を打ち砕く。いったい何の話をしているのか分からず、陳列された出来事の価値がわからないから。それでいて、いけないことをしているという罪悪感を引き起こす。私にはわからない二人の秘密の会話を盗み聞きしていることを知らしめるから。 可愛がっていた姪を海にさらわれ、授かっていた子ども我が子とするのを諦めた妻と、その妻と別れ、我が子を姪として育てた夫の書簡は、妻の生が終わるまで続く。 小さな事実を想像しながら読むのは、色褪せた写真を捲るかのようだった。
ネタバレを読む
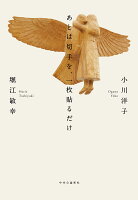
あとは切手を、一枚貼るだけ
小川 洋子/堀江 敏幸
本棚登録:0人
面白かったし、なんだか痛快だった。 実は中野氏の著書を読んだことがあって、それはなんだかなあと思わずにいられなかったので、今回の対談本は期待をいい意味で裏切ってもらった。 違う分野で極みを目指す人と言うのが掛け合わさるとこんなにも話題が拡がっていくのか、と驚いたし、それまで周囲と馴染めずにただ自分が求める領域に潜っていくしかなかった、という経験が共通するというのもなんだか頷ける。こういった人たちに憧れを抱かずにいられないのは、自分が何者でもなく(そう感じていて)、自分の中の芯というものを未だに探し続けているからかもしれない。また彼女たちを素敵だと思うことに、自分の意見を表明することに大きな葛藤を抱いてないことだけでなく、誰かを面罵しているわけではないということだ。前向きにコミカルに、でもロジカルに話を進めていこうとするその姿勢に憧れる。 思った以上にいい本だった。手元においておきたい。

パンデミックの文明論
ヤマザキマリ/中野 信子
本棚登録:0人
小川洋子氏が、科学者の先生方に感動したように、こういった科学を文学で繋ぐ人がいるのかと感嘆した。少女のような伸びやかな感性から描かれる科学の描写は、美しく、科学とはこんなにも素敵なものだったのかと思わずにいられない。 家庭の医学を好んで読んでいたという話では、わたしには気持ち悪くて読めないだろうなと思たっときに、わたしは誰にその感性をもらったのだろう?と疑問に思った。まっさらな感性で見たとき、本当に気持ち悪いと思うだろうか。もちろん思うかもしれないが、どうにも「そんなものは気持ち悪いから読むのはやめなさい」と誰かから押し付けられた感性を今の今まで大事に抱えていたような気がする。 ここから、各先生方の本に食指を伸ばすのもまた一興。その名の通り、私の中の科学への好奇心をノックしてくれる、いい本だった。

科学の扉をノックする
小川洋子(小説家)
本棚登録:0人
どちらかといえばファンタジー? 少女たちの内心を森として表現するのは面白いけど、少女たちをもう少し丁寧に追いたかった気もする。 戦争が始まって大人の思惑で隔離される少年少女という設定は匂わす程度でもいいのかなあ。舞台設定的には納得いくけど、本質と少しずれる気がして、伝えたいこともわかるし、内包する痛みや怒りもよくわかる。それ故に、森という設定がそれを具にするのでなく、ぼんやりとしてしまったように感じる。 耽美的な文章や語句は美しいが、フォントがひどく気に障る。特にひらがなの「お」。物語の雰囲気に合わせたいのはわかるが、没入感を遮られるのが嫌だった。歌集とか詩集なら良かったのかもしれない。

森をひらいて
雛倉 さりえ
本棚登録:0人
中々楽しめた。北村薫の本だから外れるなんて思ってなかったけど。 読み終わると、ああそうこの静かな文体が北村薫だなあと感慨深かった。中学生時代にスキップなどを読んだことを懐かしく思う。水面のような静かさで波紋が広がっていくような文体はとても穏やかで気持ちがいい。 主人公は40代になろうかという独身の女性。この年齢がなんともいい。華々しくもないが人生達観するにはまだまだ早すぎる。女性にとっては、時に想像する未来、もしくは過去の自分だ。 人生の大部分は大きな出来事で大きく何かが変わるわけではない。ただ毎日の繰り返しが続いていく。その中で、少しずつ疲れたり、何年も前に抱えた古傷が時折痛んだりする。人間は誰しも何かが欠けている。欠けている隙間を人は埋めたがる。その隙間を埋めたものでまたその人が彩られていく。 それを垣間見させてくれる小説だった。

八月の六日間
北村薫
本棚登録:0人
なんだかちゃっちゃか読んじゃったせいでよくわからなかった。でも、時間が食べられる、というのは面白い。 エンデのモモが時間泥棒による社会の変化を重視して書いてると考えれば、こちらはもっと科学的な観点からの社会上では時間というなんとも実はよくわかってない、稀薄な概念を共通のものとして成り立っている社会への風刺というのか。時間に人間は縛られているが、正確には好んで縛られに行ってるんだろう。
ネタバレを読む
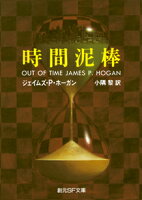
時間泥棒
ジェームズ・P.ホーガン/小隅黎
本棚登録:0人
美しい都市と醜い都市を区別するというのは、非常に難しい。端的に言えばそういう本。ただ、多くの例示から、では自分にとっての、建築美醜判断はどこだろう、と考えさせられる。答えが明示されるわけではないが、無知蒙昧に、「権威が言ってるから」とか、「ヨーロッパの建物は美しいから」とかいう何回も何回も見せられた刷り込みの考えを是とすることに対しての批判である。結果的に美醜の判断が上記と同じ結論に行き着くのは自由だが、本当に美醜の基準が自分の中にあればその論はしっかりと説明できるだろう。 はっきり言って、私は建築の美醜がよくわからない。ただ、「これが建築美ってやつです」という押し付けがましい美醜論がなんだか気に喰わないという気持ちだけ持っていた。それで読んだわけだが、答えがあるものでもないので、肩透かしを食らった。まあ安易に人の基準を貰おうと思った私が悪い。 北朝鮮の建築については中々考えさせられるものがあった。勝手なイメージで、その国の建築を見るものではないな、と思わされた。

美しい都市・醜い都市
五十嵐太郎
本棚登録:0人
最初は正直読みにくかったというか、とっつきにくく、話が理解できなかった。5万年前の死体が見つかって謎が謎を呼ぶような展開になって、面白く感じた。最初は本書の舞台がどうなっているかという説明だからだろう。あと、解説でも人物の心理描写の問題点が書かれている通り、心情に陶酔しながら読むタイプの読者にはちょっとつらいものがある。それでも、理詰めでどんどん進んでいく仮説の展開は、思いもしない未来の空想を予感させて楽しい。あと、私達が以下に仮定で進んでいる話を学校で教えられたからと言って信じ込んでいるか、ということが思い知らされる。教えられたことが間違っている、という話ではなく、教えられたことを間違っていないと主張しようとしたとき、その理屈となる背景や論説が自分の中から何も出てこない、つまり、よくわかってないけど、学校で教えられたからそうなんだろう、という思い込みで生きてきたんだと如実に思わされる箇所が多かった。SFは殆ど読んでこなかった人間だが、とても面白かった。続編もあるようなので、読んでみたい。
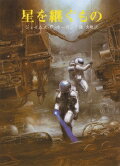
星を継ぐもの
ジェームズ・P.ホーガン/池央耿
本棚登録:0人
非常に良い本だった。あまり期待しないで読みはじめた。田舎暮らし、時代的な鬱屈さや社会構成に縛られた中で、ペスト禍が起こる。その中での混乱や、恐怖、すがる気持ちや、攻撃的な行動も、なんとも手にとるように分かる。後から、平和なさなかであれば、そういった行動や人間の営みを馬鹿らしいと一笑に付すこともできるだろうが、コロナ禍を経験した人たちは決してそうはできないだろう。人間とはどうにも愚かでひたむきな、そういう生き物だ。今どきの若者は、だとか、人間の性質が変わったかのような物言いもあるけれど、ある種私達はこの年代から、何も変わってないんだろう。それを進化のない愚かさだと取るか、人間讃歌に通じるものだと取るかは人それぞれだろう。その変わらなさに、私はなぜだか安心したし、彼らがそうでも生き永らえ、この時代まで綿々と引き継がれているものがあると考えれば、希望はまだあるようだ。 主人公のアンナに拍手を。

灰色の季節をこえて
ジェラルディン・ブルックス/高山真由美
本棚登録:0人
性に対する奔放さというのか、今とは全く違った価値観が面白かった。ただ中盤からいきなり心霊的なものが出始めて呆気なく終わった感じ。なんか、えっ、ってなって終わった。

傀儡
坂東眞砂子
本棚登録:0人
あー、村上春樹だなあと思う本だった。 正直、村上春樹の小説は好みでなくて、乾いた文体(決して貶してない)がどうにも私には上手くはまらない。ただ、エッセイとして気軽に読むぶんには面白かった。疲れてる中で、のめり込むというよりはただぼぅっとテレビを眺めてるのに似てる気分。

おおきなかぶ、むずかしいアボカド 村上ラヂオ2
村上春樹/大橋歩
本棚登録:19人
説明の仕方の取説としてはとても良いと思う。ただ、それで厳密に言えば間違った知識を広げてしまうことに対し、留意が少ないのは気になる。何故専門家の言葉はわかりにくく、インフルエンサーの言葉はわかりやすいのかに通じるものだが、立場によってはよしとできないものもあるだろう。

「分かりやすい説明」のルール
木暮太一
本棚登録:0人