WIDE_C
レビュー
300年前の本か~ すごいなぁ。風刺がそのままガリバーだか作者だかにも跳ね返っていく人間味が、それが廃れないのだと思った。 リリパットしか知らなかったけど、4つの旅の話①小人国②巨人国③空飛ぶ島④馬の国 ね。シンプルでわかりやすい
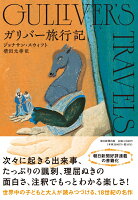
ガリバー旅行記
ジョナサン・スウィフト/柴田元幸
本棚登録:0人
金原ひとみさん、「蛇にピアス」しか読んだことなくて、しかもそれも自分が中学生ぐらいのときだったのでめちゃくちゃ久々に読んだ。 コロナ禍周辺の女性主人公の短編集 現代的なメンヘラ女子が出てくる〜みんな擬態してるから分かりづらいけど実際結構いると思うようなおんなたち アル中、整形依存、不倫、希死念慮、セックス依存、 どれも描写が上手くて的確でこの時代の痛みを切り取っている。ちょうど真ん中に配置された『コンスキエンティア』という作品が金原ひとみさんの旨み感が高まってる作品だったように思う。蛇にピアスもこんな感じだった記憶。主人公の受け身さ、暴力も含めた関係性の割り切れなさ。(なんか千葉雅也がエロスの基本は受け身とかいってたような…を思い出していた)村上龍感もある「コインロッカーベイビーズ」の空気感と似てるとも思った。 汚さや、醜さ、ちっぽけ、何もうまくできないけどうまく繕っているふう、セックスをする生き物、本当は形なんかないんだろうが、メイクをして外と中を分ける膜を作ってなんとか生きている、それが案外力強く

アンソーシャル ディスタンス
金原ひとみ
本棚登録:38人
ちょうど読んだ今まさに3月で春の気配がある。 そんなときにピッタリの本だった。 土いじり、花壇、ヒヤシンスから始まって 料理、音楽、恋愛などの描写が生き生きと美しくて五感が嬉しい読書感でした。なんか開放的な空気も感じた、誠春の空気か オルタネート自体はそんなに主張してなくて、あるもの、って感じ 料理の大会も、そういう番組見慣れてるからめちゃくちゃ脳内再生余裕でした。 最後に親が声かけてくるとこで泣いた。 何人かの話が交互に出てくるんだけど、どのキャラクターもちゃんと身があるし全くスカスカてない、むしろめちゃくちゃ豊かで本当にすごいなと思った。

オルタネート
加藤シゲアキ
本棚登録:0人
はじめの方、読んでるときに川上未映子さんの『ヘヴン』をちょっと思い出した。 途中から違う女の子視点になって、最後に2人が交わるかんじの構成 障害を持つ人への関わり、相模原障害者施設殺傷事件、多くの人がしているであろう無関心、ゆるやかな差別、その描写がありがちで痛い。 「勝手に境界線引いてるだけで、安全圏なんてどこにもねぇからな」 「普通の人がまたごく普通に酷いことしている、何となく自分はまた一人ぼっちだ」

何食わぬきみたちへ
新 胡桃
本棚登録:0人
文庫X として本屋でよく見る謎の本〜としてずっと認識してたんだけど、今エルピスってドラマが面白いらしい…の原作?がコレって聞いて読んで見たくなって購入 めっちゃくちゃ入り込んで久々に一気読みしてしまったわ…冤罪、もし自分だったらって考えると恐ろしく怒りあり、そして悲しかった。昔読んだ『沈まぬ太陽』と、ポン・ジュノ監督の「殺人の追憶」を思い出した。 自分が国、政府のことを常に信じ切って安心してるけど、国や政府だって完璧じゃないんだ人間がやってるんだから。この本読んでなかったら、そんな考えも消されていたな。(恩赦という制度を知ったときに私は国って適当なんだなってショックだった。) 殺人事件の真犯人が野放しにされてるっていうのも衝撃だよな…意外といるのかもしれない。なんかもう今の時代は犯罪したら絶対に捕まるって思っているけれど(その意識は抑止力にはなっていると思う。) この前の宮台真司刺した犯人見付からないのもビックリだよ。 しかしノンフィクションっておもしろいよな〜

殺人犯はそこにいる
清水 潔
本棚登録:0人
呪いと祝いについて考えていたときにネットで検索したら出てきたので購入。 色々な話が出てきて面白かった。予祝、国褒め、呪いを解くためにわざと物語を脱臼させる、トリックスター 日本の色々な仏教の宗派の人の人相みるのもも面白い。なんとなく仏陀には興味あったけど、日本の仏教はその場にあわせて変えた二番煎じのような気がして興味なかったが、自分が大人になってみるとそうやって柔軟に変化してるのとか面白いじゃんと思うようになったかも。

【バーゲン本】現代人の祈りー呪いと祝い
釈 徹宗 他
本棚登録:0人
40年前のエッセイだった半世紀前! 今ツイッターで呟いたら速攻炎上しそうだな〜と思いながら読んだ。糸井重里は炎上してたけど、村上春樹は絶対にSNSなんて使わないから炎上しない。そこが違う。 若い女のコへの自意識がすごい

村上朝日堂 はいほー!
村上 春樹
本棚登録:0人
一般的にこうでしょと思うような事を一喝してくれるので面白い。以下に自分が何も考えず何となくイメージした社会に忖度して思考してるか痛感する。 初めの方は専門用語や知識かないとわからない話がバンバン出てきて、全然理解してない自分はまじで宮台真司が馬鹿にする存在そのものじゃないか~など考えるほうが頭を占めてしまった。読み進めると色々なネタの中には自分もわかる身近に感じる問題も沢山あり面白かった。 しかし2015年なのでちょっと古い。宮台真司の本はリアタイで空気感感じながら読みたいな〜などと思っていたら、宮台真司が何者かに襲われた事件がニュースになっていた。そんな時代…

社会という荒野を生きる。
宮台真司
本棚登録:0人
なんかこんなもんでいいんだよ〜 気楽にいこうぜってかんじでよかった。 やっていきたい。楽しいっていうのが重要 経済が単純だったらまじでこれなのに、 現実にこんな波があるのは銀行とか国がないお金をバンバン出してるせいなんじゃないの、と思った。わかんないけど

バビロンの大富豪
ジョージ・S.クレイソン/大島豊
本棚登録:17人
かなりすごい体験をした。という読後感 読者はこの一族を見届けるゴースト的な立場でいたのかもしれない。それも著者の世代だけでなく、もっと昔から 日本人の自分から読むと家族の中でもそれぞれの個が尊重され、悪い事をしたとしても家族の愛があったりすることに違和感を感じてしまって、日本はかなり極端な考えが普通になっていて自分もその中で疑問を持っていないと思った。日本は死刑があって、死刑囚の家族がマスコミ、週刊誌に晒されることがあるけれど、悪いことをした家族に対して愛を持つことなんてないと言う感じ、またそんな悪人を出した家に問題があり、家族全員幸せに暮らすことは許されないという空気感がある。だから著者が(絶対に葛藤はあったにせよ)兄を別の人間としてドライに分析していて、他国の話だなと感じた。もし日本人が書いたら自分の責任や後悔、自己批判を言い訳としてはさみながらじゃないとかけないんじゃないかな。 アメリカにはたくさんのゲイリーかいる。同じように問題を抱えた人がたくさんいるって言ってるのもすごい。その通りなんだと思う。これももし日本だったら、この人がやった理由を他の人には芽生えようがない事だったという感じにしちゃって、たから同じことがおこることはない。終了〜 ってやってしまう。 たくさんのゲイリーがいるからこそ、こうやって切り開いてオープンにすることがとても変わっていく力になるのだろうな。 そして読者も追体験し、傷を受けることで変わるんだろう。
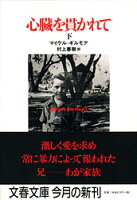
心臓を貫かれて 下
マイケル・ギルモア/村上 春樹
本棚登録:0人
悲惨な、崩壊した家族の細かい記録 しかしこのような家族は見えないだけで結構あるんじゃないのかとも思う。 家庭内暴力、親の支配、犯罪行為。

心臓を貫かれて 上
マイケル・ギルモア/村上 春樹
本棚登録:0人
石田衣良さんの本あまり読んだことないけど、ラジオが好きで聞いていたので読んでみようと思って読んだ。 ラジオで本人を知ってしまっていたので、どうも本を読んでいてもキャラクターより石田衣良本人の口調のような感じがしてしまった…。「ぼく、〇〇なの」とか中学生いうかな〜あとやたらマセてて上品なのとか、東京の中学生はそんなかんじなの?自分がわりと田舎のヤンキー中学だったのでなんかリアルに感じられなかったな

4teen
石田衣良
本棚登録:75人
感想言わなくていいとか、美術はかたまりとかすごい面白いしなるほど自分の選択肢が広がった感じだ。

感性は感動しない
椹木野衣
本棚登録:0人
ガキの時代をこんなに鮮明に覚えていて書き出せる人いないんじゃないか、ちょっとこれもまた違う世界というかんじだな のんのんばぁの話というよりガキの頃の話 多趣味とか色々気が散って集中できない人はちょっと励まされるかも

のんのんばあとオレ
水木しげる
本棚登録:0人
千葉雅也さんの本は、難解であろう現代哲学をわかりやすい言葉で教えてくれる。 以前「現代思想入門」を読んで面白く、わかりやすかったのでこちらも購入してみた。 勉強とは何か…というところから入って、勉強はノリが悪くなること、言語によって環境のコードから外れられないから言葉の意味を浮かす、宙ぶらりんにする、とか、現代詩とかでてきて、ああ読み応えがあるぞと楽しかった。同じ値段、パッケージでわかりやすくて簡単なHOWTO本が多く、そういうのは1.2 時間で読み終わってあんまり頭に残らないのが多いのだけど(そういうのも時として悪くない、読んだらすぐメルカリで売る。)こういう本はアタリってかんじでお得感がある。 自己の享楽やこだわりからヒントを得る。 文庫版のおまけ補章も面白かった。

勉強の哲学 来たるべきバカのために 増補版
千葉雅也
本棚登録:27人
下巻割と一気に読んでしまった。文化大革命ってほんの5.60年前なのか…今まであった中国の友達の親とかその親とかが影響受けてるんだ、自分の身近なことなんだなぁとビビるし、今でも香港の活動家とかバンバン逮捕されたりして終わってないんだなぁと思う。しかし色々SFかと思ってしまう。タンアンっていう一人一人の裏調査書みたいなのとか、今もあるんだよね?すごいなぁ…

ワイルド・スワン(下)
ユン・チアン/土屋京子
本棚登録:0人
なんとなく知ってはいたけど、本を読んで追体験していくと本当に毛沢東支配やばすぎだな〜創作SF読んでるみたい。SFで悪の親玉がまーそこまで悪いやつって創作だよね、現実味ないよねっていうのの上をいっている… 子供に残酷な暴力を推奨するのまじで悪夢だよな、子供ってあなどれんよな

ワイルド・スワン(中)
ユン・チアン/土屋京子
本棚登録:0人
名前のない女(曾祖母)→祖母の軍閥の妾イータイタイ阿片再婚→満州、日本の支配→国民党、共産党 次々に支配するものが変わり、暮らしも変わり、暮らす場所も変えていかねばならない 祖母の纏足、イータイタイの話とか波乱万丈すぎる 急激に世の中が変わって行くときに人がどうだったか。この家族は比較的裕福で高い地位の人々だが、低い地位の人々はどんどん死んでいったりしてるんだろうな。もちろん高い地位の人も死ぬし、このあと文化大革命がどうなるか…

ワイルド・スワン(上)
ユン・チアン/土屋京子
本棚登録:0人
ドアが閉まる音、鍵を開ける音、ヒールで家から出ていく音、火傷のあとの触感など、生活の手触りの描写に対して、ただ、ある死。
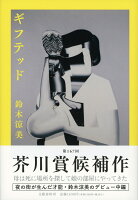
ギフテッド
鈴木涼美
本棚登録:23人
対人関係の講座やっててテキストが溜まってきてできた本。なっとく 人を立てるとか、なんかいいらしいのは知ってるけどなぁ…(やらない)っていうのを色々具体例あげてあるのみるとあながち馬鹿にできないよなぁとやってみたくなる。たしかに 本当に人と言い争ってもいいことないよって大人になるとわかってくるよね(10代20代でこれ読んでもケッってなりそう)
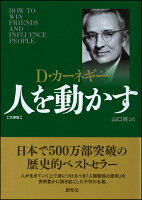
人を動かす文庫版
デール・カーネギー/山口博
本棚登録:0人